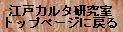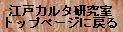
「下六光」は既出の「下五光」、後出の「下三」「下四光」等と同系統の役で、青札の下位の六枚が揃う事によって成立します。これらの役の元に成っているのは「あざ」「青二」「青三」の三枚による「下三」役で、その他は「下三」の拡大役、或いは派生役と位置付けて良いでしょう。
「下六光」役が揃う確立は極めて低い為、役点は「あつかい」とされていますが、そこに「打って」という条件が付けられています。「打てあつかい」の意味について佐藤要人氏は『江戸めくり賀留多資料集 解説』(p60)の中で、次の様に推測されています。
「打て」の意味が判然としないが、この語は「出して」という語に対する言葉のようだ。推測ではあるが、「出して」というのは、配牌後、場に晒して役を公開することではないか。この場の役点は、たとえ、上り負けしても、その権利は保有できるのであろう。「打て」は、この反対で、役のあることを隠して、勝負を挑むことと思われる。この場合は、上り負けると役点はすべて無効となる。この下六光役には「出していくつ」という役点がないので、手役公開は認めぬのであろうか。
さすが佐藤先生らしい卓見だと思いますし、この解釈に基本的に賛同いたします。「打てあつかい」の場合は上り勝てばかなりの高得点が得られますが、上り負けた場合には無得点という、言うなればオール・オア・ナッシングなのに対して、「出して」の場合は手役を公開してプレイする事によるハンディーと引き換えに、一定の得点を保証するというアイデアは理に適っています。手役を公開して、尚かつ上り勝った場合には「あつかい」に成ると考えられますが、だとすれば他の三人の競技者は何をさて置いても上りを阻止する事に全力を尽くす筈でしょうし、相手の手の内の一部が晒されている訳ですので、上りを妨害する為の具体的な作戦も立て易いでしょう。ですので、例え手札を「出して」公開する事が認められている場合でも、競技者にとってそれを選択するのが得策なのか否かは、非常に判断の難しい問題だと言えます。
ところで「下六光」の場合は「打てあつかい」とあるのみで「出して」の記述は有りませんので、恐らく手札を公開してのプレイは認められていないのだと思われますが、これは別に不思議な事では有りません。この役は青札の一から六迄の連続した数の札で構成されていますが、ひとたび自分に手番が廻って来れば一気に六枚全てを出す事が可能です。更に、もしもこの六枚を場に晒して公開したとしても同様に自分の手番で一気に出し切る事が出来ますし、しかも他の競技者にそれを阻止する有効な手立ては有りません。すなわち「下六光」の場合は、元々上り勝つ確立がかなり高いのと同時に、手役を公開する事によるハンディーが極めて少ない訳ですので、「出して」のプレイが認められないのは頷けます。
次の「ねはん」は仏教用語の涅槃でしょう(佐藤説)。これも役点は「あつかい」とされています。但し「ごみ入り」と条件が付けられているのですが、これが「白絵」の場合には「あつかい」に成らないという意味だとしたら不可解です。何故なら、他の多くの役では原則として「ごみ入り」よりも「白絵」の方が高得点と成っているからです。或いは「白絵」の場合も当然の事ながら「あつかい」で有り、「ごみ入り」の場合でも同じく「あつかい」に成るという意味かとも考えられますが、この問題に関しては、今は取り敢えず保留とさせて頂きます。
前出の「下六光」と同様に「出して」の記述は有りませんので、手役の公開は認められないのでしょうか。確かに「下六光」ほどでは無いにせよ、本役を構成する五枚の札も一気に出し切り易い組み合わせです。
次に「ねはん(涅槃)」という役名の意味する所を考えて見ましょう。前出の「竹つな」が「太鼓二」の札に描かれた竹の絵柄から連想されたと考えられる様に、幾つかの役では役名と、その役を構成する札との間に何等かの関係を見出す事が出来ます。「竹つな」の様なストレートで判り易いネーミングも多く見られますが、どうやら「ねはん」の場合は少し捻って有る様です。佐藤氏は「ねはん」と名付けられた理由に関しては言及されていませんので、ここで拙案を披露させて頂きましょう。
広辞苑によれば、涅槃には次の二つの意味が有ります。
- 煩悩を断じて絶対的な静寂に達した状態。仏教における理想の境地。
- 仏陀または聖者の死。入寂。入滅。
今回関係が有るのは後者の方で、例えば釈迦の入滅の場面を描いた絵を涅槃図と呼ぶのはこちらの用法です。
ここで再び「ねはん」の構成札を確認しておきますと、「あざ」「青二」「青馬」「青切」「太鼓二」の五枚です。しかし、いくらこの五枚を眺めても、「ねはん」と直接結び付く様なものは思い浮かばないのでは無いでしょうか。実はヒントはそこに有る五枚の札では無く、そこに無い一枚の札に有るのです。
「ねはん」役を構成する札を見ると、既に登場済みの或る役に良く似ている事に気付きます。それは、本文の冒頭に紹介されている重要な役である「五光」です。「五光」と「ねはん」の違いは何かと云うと、「釈迦十」の札が入るか入らないかという点のみで有り、つまり「五光」から「釈迦十」を抜くと「ねはん」に成る訳です。更に「釈迦十」は単に釈迦と呼ばれる場合が多い事を考え併せれば、もう答えはお判りでしょう。「ねはん」は「五光」から派生した役で有り、そこから釈迦が抜けたものです。釈迦が無くなった(亡くなった)、即ち釈迦の入滅、つまり涅槃という事に成る訳です。
続いては「三ごくてんらい」及び関連役の「三五九一」です。意味は佐藤説に従って「三国伝来」「三国一」で間違い無いでしょう。ネーミングの由来は「三国一」の方が分かりやすいと思います。青札の三、五、九、一で、実に単純な語呂合わせです。ちなみに「三国一」とは天竺(インド)、唐(中国)、日本の三国で一番という意味です。
時代はかなり下りますが、明治二十四年刊の『温古の栞 十四篇』に「三国一」役の記述が見つかりました。『雨中徒然草』の「三国一」と直接関連が有る可能性は低いと思われますが、一応ご紹介しておきましょう。
十の内一枚をシヤカと名け無上とす又三五九一の内表畫に依り一枚づゝを最勝とし是をサン、ゴ、ク、イチと名く
一方、「三国伝来」は少し検討する必要が有りそうです。三国伝来とは、天竺から唐を経由して日本に伝来して来たものを表し、例えば仏教もその代表的な一つで有る事は言うまでも有りません。従って、「三国一」役に三国伝来の釈迦を表わす「釈迦十」の札一枚が加わる事によって「三国伝来」役と成る訳です。この様に見て来ますと、この二つの役の関係は『雨中徒然草』の表記とは逆に、「三国一」役の方が元で、「三国伝来」が派生役という関係だと考えた方が良い様な気がします。ちなみに佐藤氏は、「青九」の札から九尾の狐を連想している可能性も指摘されていますが、「三国一」と「三国伝来」の違いは「釈迦十」一枚の有無だけですので、そこまで考える必要は無い様に思われます。
役点については「三国伝来」では「五ツ」と「打って あつかい」の二通りの記載が有りますが、これは「出して 五ツ」を意味するのでは無いでしょうか。つまり役を公開して競技をした場合に、例え上り負けても5点だけは保証されるという訳です。では何故、同じく五枚の札で構成される役で有っても、前出の「ねはん」の場合には「出して」が認められず、「三国伝来」では認められるのでしょうか。これは上り勝ち易さという観点から説明出来ると考えています。
問題を単純化する為に、役を構成する五枚だけに絞って比較して見ましょう。先ず「ねはん」ですが、「よみ」の推定ルール及び「あざ立て」の推定ルールに従った場合、手番が「二」か「馬」の時は五枚を一度に、「切」及びそれ以外の数の時でも四枚を出す事が出来ます。
これに対して「三国伝来」の方は手番が「三」「五」「九」の時で四枚、それ以外の数の場合に出せる枚数は三枚のみです。
この様に、同じ五枚で構成される「あつかい」役でも、上り易さという点ではかなりの差が有る訳です。「ねはん」の様に上り勝つチャンスが十分有る場合には、何も手札を公開してプレーする必要は有りませんが、「三国伝来」の様に自力で上り勝つ可能性が低い場合には、一旦手役を公開して最低限の得点を確保しながら、あわ良くば上り勝って「あつかい」をゲットしようという作戦は大変魅力的です。しかし繰り返しに成りますが、その場合には他の競技者による最大限の妨害を覚悟しておかなければなりません。
しかし「三国伝来」役が揃っている時には常に上りが難しいと云う訳では有りません。残りの四枚の手札に「二」「四」等の間を埋める数の札や、「馬」「切」が入って全体として連続した数の札が揃えば、上手く行けば一手で打ち切りに成る場合も有ります。その場合には手札を公開するメリットは余り有りませんので、手役を出さずに「打って」いく戦法を採るべきでしょう。
「おふとう」は「お不動」(佐藤説)でしょう。この四枚で何故「お不動」なのかはよく分りませんが、「青切」のデザインが、降魔の利剣を手に持つ不動明王像を連想させるのかも知れません。
この役には「馬」の札が三枚含まれています。通常、「馬」三枚が揃うとよみ技法の特殊ルールで有る「崩し」の一つで有る「馬崩し」が成立し、その回のゲームを無効として終了する事が出来るのですが、「馬崩し」が成立しない例外が規定されています。
「同じ心なり。もっとも、切有りては崩しに成らず。」
つまり、「馬」三枚と一緒に「切」の札が有ると「馬崩し」の権利が無くなるという事で、その理由については以前考察しました。但し、それが「青切」の場合に限っては、「崩し」を行使する権利剥奪の代償として、「おふとう」役という救済措置が認められる事に成ります。
役点の記載は有りませんが、単なる記載漏れなのか、或いは直前の役と同じ場合に記載が省かれている可能性も有ります。だとすれば「三国伝来」と同じく「出して 五ツ」「打って あつかい」という事に成ります。「お不動」と似たタイプの役に後出の「惣十郎」が有りますが、役点は「出して 四ツ」「打って あつかい」とされていますが、これと比較しても不自然とは思えません。
『雨中徒然草』本文の全般的な構成は、似通った役、関連の有る役をまとめて紹介すると云う編集方針の様です。この二つの役もよく似ており、違いは「青切」と「青馬」が入れ替わっているのみで、役点も白絵で3点、ごみ入りで2点と全く同じです。
ここでの問題は、役名「こんてい」の意味です。この解釈については佐藤氏も悩まれた様で、最初『季刊古川柳』に連載された『かるた目付絵雨中徒然草』の時点ではこれを「昆弟」では無いかと推測されていましたが、『江戸めくり賀留多 資料集』では「金泥」と改めておられます。しかし、これも確信は持てないと見えて「金泥か。」とされています。確かに両案共に、どうもしっくりしない感が否めません。「昆弟」とはあまり聞き馴れない言葉ですが、兄弟という意味だそうです。果たして江戸時代には一般的な言葉だったのでしょうか。佐藤氏自身が後に取り下げている事からも、あまり有力な説とは思われません。「金泥」とは書画を金彩色するのに用いる金絵の具の事で、「こんでい」と「きんでい」の二通りの読み方が有ります。確かに江戸カルタの七金物の金彩色には金泥が使用されていますし、「こんてい」役を構成する三枚の札はどれも七金物です。しかし、七金物の札のみで構成される役は他に幾つも有る訳で、この三枚の組み合わせに対してのみ、敢て「金泥」と名付けるべき根拠は思い当たりません。
「昆弟」「金泥」両説共に有力とは言えない状況の中で、もう一つ仮説を提出させて頂きましょう。ここで「こんてい」役が「天上」役と類似点が多く、関連が深いと考えられる点を思い出して下さい。仮にこの二役が一対を為すもので有るなら、役の名称に関しても何等かの関連が有っても良いのでは無いでしょうか。そこで思い当たるのが「根底」です。「天上」と「根底」は厳密な対義語とは言えませんが、ほぼ反対の概念で有る事は間違い有りません。更に「天上」が天上界、つまり極楽を意味するのに対して、「根底」は地獄をイメージさせます。そこに「馬」札が入るのは地獄の六道の一つである畜生道からの連想では無いでしょうか。
この二つの役は、正に一対を為す役と言えます。青札の上位三枚で「上三(かみざん)」、下位三枚で「下三(しもざん)」。役点は共に白絵の場合で3点、ごみ入りで2点と成っています。両役共に「めくり」技法の出来役にも採用されている事もあって、江戸文芸にもしばしば登場しています。但し「よみ」の役としての使用例に限って見ればそれ程多くは有りませんが、古くは享保年間にその存在が確認出来ます。
「そういき」は後出の役「惣生」、「かみざん光」は「上三」の事と考えられます。「天地」は『雨中徒然草』には登場しませんが、やはり「よみ」の役名であろうと考えています。根拠となる資料をご紹介しましょう。
例によってカルタ用語尽しの趣向の一部ですが、特にこの部分は「三馬」「二くづし」「四切」「七坊」「五むし」と、全て「よみ」の役名が織り込まれています。その間に挟まれている「天地」も又「よみ」の役名で有る可能性が高いと考えて良いでしょう。
『一句笠』に戻りますが、「かみざん光」とされている点にご注意下さい。「上三」という名称は上の三枚による役という意味では無く、元々は上の「三光」という意味の「上三光」だったものが省略されたものと考えられます。
三鈷(さんこ)は密教で使用される法具の一つですが、ここではカルタの「三光」役に掛けているのは明白です。同様に「上ざんこ」「下ざんこ」は「上三光」「下三光」という事に成ります。「下三光」と表記すれば直ぐにお気付き頂けると思いますが、実は「下三」は既出の「下モ五光」「下六光」、及び後出の「下四光」等と同系統の役であった訳です。「下六光」の項でも触れましたが、これらの役の中で元に成ったのが「下三」であり、その拡張型派生役として「下四光」以下が考案されたという経緯が考えられます。
次に登場する二つの役も、「下三」からの派生役と言えそうです。
「上三」「下三」に続いて「中三」と来れば、青札の中程の三枚かと思えばさに非ず。「下三」役の「青二」の代わりに「太鼓二」が入ると「中三」に成る訳ですが、何故これで「中三」なのかは良く解りません。「下三」の真ん中の札が代わっているという事でしょうか。役点は白絵で2点、ごみ入りで1点です。補足説明の部分を見てみましょう。
この絵の外に
四、入れば中四
五、入れば中五
下五光に同じ
もっとも石一つ増しに取る
意味としては、この三枚に加えて青札の4が有れば「中四」、更に青札の5も有れば「中五」役と認められます。これは「下三」役と「下五光」役との関係と同じ事ですが、役点は「下三」系の役の方が一点づつ高く成っているという事でしょうか。記述が簡潔過ぎて曖昧なので別の解釈も可能かと思われますが、取り敢えずこの様に考えておきましょう。
「へに三」は恐らく「紅三」でしょう(佐藤説)。「下三」役の「青二」の代わりに「海老二」が入ると「べに三」に成ります。「海老二」札は「よみ」技法で唯一使用する赤絵の札ですので、「紅」の字を充てるのが妥当でしょう。「中三に同じ心なり」と有りますので、恐らく青札の4、5の札が加わる事によって「べに四」「べに五」等の役が認められるのでしょう。役点も「中三」と同じです。
「海老二」を構成札に含む役としては、この「べに三」が初登場と成りますので、ここで「海老二」札の役割について再度考えて見たいと思います。佐藤要人氏は「海老二」を「大極札」と呼び、「自由自在に変身する特殊札」で有ろうと推測されています。この説に対しては序文の解説の中で疑問を呈しておきましたが、この「べに三」も佐藤説への反証の一つと成るものです。
理由は簡単です。もしも「海老二」が他の札に変身出来る化け札であるならば、「べに三」の「海老二」札を「青二」として使用する事により「下三」役と成ります。「べに三」よりも「下三」の方が役点が高いのですから当然そうするべきでしょう。つまり、「べに三」という役の存在自体がナンセンスと成る訳です。これと全く同じ事が次の「海老蔵」に関しても言えます。「海老蔵」の構成札は「あざ」「海老二」「釈迦十」の三枚ですが、この「海老二」が「青二」に早変りすると・・・もうお分かりですね。目出度くも「団十郎」襲名と相成る次第です。
「えひそう」は「海老蔵」で間違い無いでしょう。そして「海老蔵」とは言うまでもなく、歌舞伎の名跡の一つで有る市川海老蔵の事と考えて良いでしょう。市川海老蔵は市川団十郎と関係の深い名跡で、例えば初代市川団十郎は団十郎の前に海老蔵を名乗っていますし、二代目団十郎は逆に団十郎の後に海老蔵を襲名しています。
「よみ」の役としての「海老蔵」も又「団十郎」と密接な関係に有ります。「海老蔵」役の構成札は「団十郎」の「青二」が「海老二」に代わったものです。つまり「海老蔵」は「団十郎」からの派生役と位置付けられ、更に「海老二」札が入るので「海老蔵」と、実に分り易いネーミングだと言えますが、一つ考えておかねばならない問題が有ります。タマゴとニワトリの命題では有りませんが、「海老蔵」が先か「海老二」が先かという問題です。つまり、先に「海老蔵」役が考案され、その結果「赤二」の札に海老を描いた札が作られ、更に「海老二」という呼称が広まったという過程を取った可能性も有る訳です。
市川海老蔵の名跡は、初代市川団十郎が団十郎を名乗る前に使用していた名前ですので、実は団十郎よりも古い訳です。しかし、その当時は海老蔵という名前の知名度はそれほど高かったとは考えられませんので、「よみ」の役名に使用される可能性は低く、有るとすれば二代目団十郎が後名として海老蔵を襲名して以降と成ります。「団十郎」役の解説部分でご紹介した様に、この頃既に「団十郎」役の名称が使用されていたとすれば、超人気役者で有った二代目団十郎が海老蔵に改名した時点で「海老蔵」役が考案されたとしてもおかしくは有りません。しかし、前提と成る元禄期における「団十郎」役の存在という事自体が一つの仮説に過ぎず、『雨中徒然草』での初出迄のおおよそ七十年の間に「海老蔵」役の存在を示す痕跡が全く見当たらないという資料事実から見ても、あまり現実的だとは思われません。やはり、先行して「海老二」札が誕生し、それからの連想として「海老蔵」役が考案されたと考える方が妥当だと思われます。
続いての問題は「海老二」という呼称の誕生した時期と、海老の絵が描かれた札の作られた時期との先後関係です。
本句の内容から、遅くとも宝暦末以前に「海老二」或いは「海老」の呼称が使用され、恐らくは海老の絵柄入りの札が存在したであろう事が想像されます。「海老二」の名称の登場以前は、他の札と同様に単に「赤二」と呼ばれていた様です。尚先述の如く、布袋屋のカルタの「赤二」札には布袋和尚の絵が描かれていた事が『軽口あられ酒』宝永二年(1705)や『絵本富貴種』明和六年(1769)等の資料から知れます。
『絵本富貴種』は『雨中徒然草』と同時期の刊行ですので、「海老二」札の登場以後も布袋屋カルタには布袋の絵柄が使われ続けていたのは確実です。『雨中徒然草』のカルタは笹屋系と推測されますが、最初に「海老二」を考案したのが笹屋なのか、或いは他のカルタ屋なのかは全く見当が付きません。もしも海老の絵柄がカルタの製造元を示すトレードマークとして考案されたものならば、例えば、海老屋という屋号を持つカルタ屋でも有ればいかにも怪しいのですが、残念ながら今のところその様なカルタ屋の存在を示す資料は見当たりません。
次に、もう一つ別の角度から「海老二」札の成立過程を考えて見ましょう。先ず「赤二」札の別称として「海老二」という呼称が誕生し、その呼称に合わせる形で海老の絵柄の札が作られたという順序です。
ここでは「赤二」札の赤い二本の棒を、伊勢土産の赤い塗り箸に見立てています。この「見立て」というのは江戸時代人の大得意とするところで、カルタ札の特殊な呼称の幾つか、例えば「太鼓二」「おかわの二」「釈迦十」等はこの「見立て」に基く名称です。特殊な呼称を持たない「青二」についても、川柳子は色々な物に見立てています。
本題に戻り「海老二」の由来を考えるならば、恐らく二本の赤い線を海老の髭に見立てたのでは無いでしょうか。そして「赤二」の別称として「海老二」という呼び方が広まった事を受け、海老の絵を描いた「海老二」札が創り出されたり、「海老蔵」役が考案されたりしたという経緯が考えられます。可能性としては、この順番が一番有り得そうだと思っているのですが、確認されている資料が極めて少ない現状では、あくまで想像の域を出るものでは有りません。
構成札は「釈迦十」「コップの十」「オウルの十」の三枚ですが、「白絵」の場合にと云う条件付きです。もしこの条件が付かなければ、単に後出の揃役の一つに過ぎず、役点は僅か3点ですが、ここでは「出して 四ツ」そして何と「打って あつかい」の大盤振る舞いと成っています。この意味する処の検討の前に、役名について見ておきましょう。
役名「惣十郎」の読みは「そうじゅうろう」で良いでしょう。これは佐藤氏もご指摘の通り、歌舞伎役者の沢村宗十郎に由来するもので有る事も、ほぼ間違いないと思われます。沢村宗十郎は現代迄も続く歌舞伎の大名跡の一つで、特に初代沢村宗十郎(1685-1756)は二代目市川団十郎と同時代に活躍し、人気を競い合った名役者です。『雨中徒然草』の刊行当時は二代目宗十郎(?-1770)の時代に当りますが、彼も又当時の人気役者でしたので、人々の間で沢村宗十郎の名は広く知れ渡っていたと考えて間違い無いでしょう。
ここで一つ考えておかねばならないのは、役名の呼称「そうじゅうろう」を文字表記しようとした時、多くの人が先ず最初に思い浮かぶで有ろう「宗十郎」では無く、敢て「惣十郎」としたのは何故かという問題です。その答えは、役の構成札が「十」の札三枚である事から容易に察しが付きます。つまり「惣」は「総」と同義で「全て」という意味ですので、全て「十」の札で「惣十郎」という訳です。では、只それだけの理由で「惣十郎」という表記が選ばれたのかというと、そうとも言い切れない問題が有るのです。実は、享保五年(1720)に初代が沢村宗十郎を襲名する直前の数年の間、沢村惣十郎と名乗っていたという事実が有るのです。もしも、その事迄も承知の上で「惣十郎」を使用したのであれば、著者である太楽なる人物は、実は中々の歌舞伎通だったのかも知れません。
役点は「出して 四ツ」「打て あつかい」とあります。「打てあつかい」は既に何度か登場済みですが、「出して」については既に何度か触れて来ましたが、具体的にはここで初めての登場と成ります。「出して 四ツ」の意味は佐藤説に従い、役を場に公開してプレイする事によって、例え上り負けても4点だけは獲得出来るものと考えます。ここで注意しておくべき点は、この役の成立条件が「白絵」に十の札三枚という事で、つまり「惣十郎」役を証明する為には九枚の手札を全て公開しなければならない訳です。手の内全てを晒した状態で、尚且つ上り勝つのは不可能に近いのでは無いでしょうか。しかしながら、実質的に上りを放棄して迄も、確実に「出して 四ツ」を確保するのは決して損な戦法では無いと思われます。
「惣十郎」役は、仮に役を公開せずに勝負したとしても上り勝つのが非常に難しい手だと考えられます。何故なら手札に同じ数の札が三枚有る場合、原則として三枚全てを出し切る為にはその数での手番が三度廻って来る必要が有るからなのですが、「よみ」の推定ルールでは例外として、手番で「切」を出した場合には次に任意の札を出す事が出来ると考えられます。もう一つの例外が「あざ立て」で、手番で「あざ」を出した後に任意の札を出せると推定されます。つまり「切」「あざ」更には残りの札の組み合わせがうまく機能した場合には、三枚の同数札も比較的少ない手数で出し切る事が可能と成ります。しかし、ここで思い出して頂きたいのは「惣十郎」の成立条件が「白絵」だと云う点です。これは残りの手札に生き物札が含まれていない事を意味しますので、当然の事ながら「切」も「あざ」も無く、従って三枚の「十」を一枚づつ地道に処理していくしか有りません。
こうして見ると、同じ「あつかい」とされる役にも幾つかのタイプが有る様です。大まかに分類すれば、一つは「五光」や「下六光」の様に手札に役が揃う確立は極めて低いものの、一旦役が揃えば比較的容易に札を打ち切って上り勝ちし易いタイプ。もう一つは「惣十郎」の様に、役が揃う確立は相対的に高目ですが、上り勝つ事はかなり難しいというタイプです。既出の「あつかい」役では「ねはん」は前者に、「三国伝来」は後者に分類出来ると考えられます。そして、手役を場に「出して」公開する事を認める規定は、後者のタイプの役に対する一種の救済措置的な意味合いが強いのでは無いでしょうか。勿論、出すか否かは競技者の判断に委ねられている訳で、残りの手札を含めた全体の組み合わせから判断して、より有利な作戦を採れるかが競技者の腕の見せ所です。このルール一つを見ても、改めて「よみ」技法のルールが高度に戦略的で奥の深いもので有る事を強く感じさせられます。