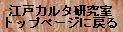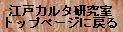
江橋先生は本稿の最後で、『教訓世諦鑑』に対して「記述の信頼性はあまり高くない」「カルタ遊技史の文献史料としては第一級のものとは言えない」という評価を下し、「このような文献史料を基礎に置いて歴史像を立論するのは危うい」と断罪されます。
当方は『教訓世諦鑑』を“合せ=めくり系技法説”の重要な根拠の一つと考えてます。更に“よみ”に関する重要な基礎資料でもありますし、謎の技法“長半カルタ(仮称)”に関する唯一の具体的な記述でも有り、カルタ史研究に於ける一級資料の一つだと捉えています。又、前稿で示した通り、カルタ以外の諸賭博に関しても江戸前期の数少ない資料の筆頭に上げられる貴重な資料だと考えます。
そう云う訳で当方としては、江橋先生による『教訓世諦鑑』及び著者である執中堂西山に対する謂れ無き冤罪を晴らすべく、全力を傾けて弁護をしたいと思います。尚、弁護人という立場上、どちらかというと被告側寄りの弁証に成る事と、原告である江橋先生に対して攻撃的な論調に成らざるを得ない事はご理解下さい。双方の主張を公平に検討し、どちらの主張が妥当なものであるのか、最終的な審判は読者の皆様に委ねるしかありません。
この後の論考では、最初に『教訓世諦鑑』の原文を揚げ、それに対する江橋先生による批判と、当方の反論を記すという形式を採ります。尚、便宜上幾つかの段落に分けさせて頂きます。
(1)全体の構成について
我国のならわし、哥留多と云へる、数四十八枚あるものをもつて、勝負の品をわかつに、半のかずに、三五七九と、あたるを勝とし、二四六八を、皆まけとす。是ハ哥留多三枚をもつて、其長と半との印を見る。爰において、かう、おいてう、など云へる、色々の名あり。
先ず江橋先生は、文章全体の構成に係わる問題点から論じられます。
貝原は、「博奕(はくゑき)」の項では、まず「哥留(かる)多(た)と云へる、数(かず)四十八枚あるものをもつて、勝負(しやうぶ)の品(しな)を、わかつに」として、三枚の札で丁半を判定する「かう」「おいてう」その他いろいろな名のあるカルタ博奕を紹介している。これを見た感想であるが、まず、ここで貝原がなぜ博奕の項の冒頭にカルタを扱ったのかが理解しがたい。
最初にお断りしておきますが『教訓世諦鑑』の著者は貝原益軒では無く、執中堂西山である事が判明しましたので、以後江橋先生が「貝原」と記している部分は適宜「執中堂西山」に直して述べさせて頂きます。
最初の批判点は「貝原がなぜ博奕の項の冒頭にカルタを扱ったのかが理解しがたい」というものです。何故それが理解し難いのでしょうか? 先を見ましょう。
古来、代表的な博奕は骰子博奕と盤雙六であり、鎌倉時代、室町時代などの文献史料や絵画資料などでは、取り上げられているのは骰子博奕か盤雙六である。
たしかに古代から中世にかけて、我が国の賭博の花形が「盤雙六」であった事は「文献史料や絵画資料」から間違い無い事実だと認められます。しかしそれはせいぜい中世迄か、ギリギリ近世初期迄の事であり、少なくとも『教訓世諦鑑』の書かれた十八世紀には双六が賭博の主役の座を退いていた事は疑い様が有りません。
ところで、中世には「骰子博奕」が双六から独立して存在した事を示す文献史料は幾つか承知していますが、鎌倉時代や室町時代の「骰子博奕」の場面が取り上げられている絵画資料って有りましたっけ? 不勉強の為思い当たりません。
カルタ遊技の賭博は、これらに比べるとずっと遅れて安土桃山時代の新参者であり、罪の程度も軽度で重罪の博奕には含まれない準博奕の扱いである。もっとも、カルタの遊技法の中で「カウ」などのカブ系の賭博は博奕並みに悪質なものと理解されていた。
“双六”や“サイコロ博奕”に比べて“カルタ”が「新参者」のであるのは間違い有りませんが、それが記述の順序に何か関係が有るのでしょうか? 執中堂西山は歴史書を書いているのでは有りません。
ところでこの後の反論に入る前に、一つお断りしておきたい事が有ります。白状しておきますが、カルタや賭博の法制史の分野に関する当方の知識が決定的に不足している事は十分自覚しております。少しづつ勉強を始めているところではありますが、現状では到底江橋先生の足下にも及ばない事は重々承知しております。以下の反論の論点にも、浅学ゆえの初歩的な勘違いがあるかも知れない事をご承知おきください。
カルタは「罪の程度も軽度で重罪の博奕には含まれない準博奕の扱い」だとか、「カブ系の賭博は博奕並みに悪質なものと理解されていた」と云う記述には正直驚かされました。当方の乏しい知識では、ここでの先生の主張が如何なる根拠によるものなのかに全く思い至りません。法制史とカルタとの両方のエキスパートである先生にとっては“言わずもがな”の常識なのかも知れませんが、当方の様な初学の者にも理解出来る様、当時の法令や判例を具体的に示してご説明頂ければと願います。
カルタに関する最古の文献史料である長曾我部元親式目は「博奕、カルタ、諸勝負、令停止」と三者並列であり、これは重罪の博奕、軽罪のカルタ、叱責する程度の雑な諸勝負の三段階で禁止したものと理解される。
何故その様に「理解される」のかが全く理解出来ません。
『長曾我部元親式目』は現在確認されている最古のカルタ資料です。土佐の戦国大名長曾我部元親が豊臣秀吉の命により朝鮮に出兵(慶長の役)する際、拠点であった北九州の肥前名護屋で待機中の兵に対して発した一連の法度の総称で、その中の一条に次の一文が有ります。
江橋先生にしては珍しく具体的な資料を示されました。文章の流れからすると、ここは前文の根拠となる資料を示すべき所だと思うのですが、実際には全く論拠に成ってはいません。
先生は文中の「博奕(サイコロ博奕)」「かるた(カルタを使った博奕)」「諸勝負(それ以外の諸々の博奕行為)」の順番には意味が有り、罪の軽重によって「三段階で禁止したものと理解される」とお考えの様ですが、この文面自体にその様に読み取れる要素は全く有りません。では、何等かの他資料による裏付けが有っての「理解」なのでしょうか? 少なくとも『長曾我部元親式目』と同時代の別資料によるもので無い事は確かです。もしもその様な資料が存在するならば、間違い無くカルタ史研究に於ける世紀の大発見ですので秘すべき理由は有りません。勿論、今後発見される可能性は十分に有りますし、是非見つかって欲しいと願っています。
『長曾我部元親式目』の文面が、サイコロ=重罪、カルタ=軽罪、その他緒勝負=微罪、と「三段階で禁止したもの」だと云う認識は、あくまでも江橋先生の仮説に過ぎず、その根拠も不明です。当方としては『長曾我部元親式目』の文面を先入観無しに読めば、いみじくも先生ご自身がおっしゃっている様に「三者並列であり」、これらを列記する事であらゆる手段の賭博行為を一律に禁止しているものだという印象を受けます。もしも「博奕、かるた、諸勝負」の順番に何等かの理由が有るとするならば、名護屋の軍営で実際に行われていた頻度と、それによる弊害の大きさ順と考える方が現実的でしょう。軍営の風紀上、最も目に余ったのがサイコロ賭博であり、次にカルタ賭博、ついでに他の諸々の賭博行為もまとめて禁止しちゃえ!って事じゃ無いでしょうか? 勿論これも仮説(想像)に過ぎませんが、少なくともこの法度の違反者に対して、サイコロか、カルタか、その他の賭博かによって課される刑罰に軽重が有ったという状況はあまり想像出来ません。
博奕の害悪を説く場合は、多少なりとも専門的な知見があれば、まず、主犯格の骰子賭博を取り上げ、次に、しばしば盤雙六を上げ、それ以降でカルタ博奕に触れるのが一般常識である。そこで、貝原がなぜこうした当時の知識人の常識的な理解に反して、博奕の項の筆頭に骰子博奕ではなくカルタ賭博を挙げたのか、その特別な思いが分からない。
これは驚きです!!
この文章によると、「当時の知識人」しかも博奕について「専門的な知見」を持つ著者によって書かれた「博奕の害悪を説く」内容の資料に基づく見解の様です。しかもそこには「しばしば盤雙六を上げ」られているとの事ですので、少なくとも数種類の資料に基づくご指摘なのでしょう。そうで無ければ「当時の知識人の常識的な理解に反して」いると断言出来る筈は無いでしょう。恥ずかしながら、先生がおっしゃる様な「骰子賭博」(しばしば「盤雙六」)「カルタ博奕」をこの順に列記した、当時の賭博に関する資料など全く思い当たりませんし、「当時の知識人」の博奕に対する「一般常識」など到底想像もつきません。
管見の内、先生の挙げられる条件に最も近いと思われる資料を紹介しておきます。
著者は不明ですが、それなりの知識人と見て良いでしょう。彼の認識では博奕の代表格は、昔は「双六」今は「加留多」の様です。残念ながら主犯格であるサイコロ賭博に関しては「孔子のいましめ給ふ博奕といふも采をうつて賭勝負をする事也」と、まるで我が国とは関係無い様な口ぶりで軽く済ませています。
又、双六に関しては「女中よりあひて伽羅なぞ賭にして双六うつハやさしくも見ゆるものなり」と、幾分共感的に見ている様ですが、カルタに関しては「よき人ハかりにも手にふれ給ふべからず」と、嫌悪感をあらわにして断罪しています。
勿論、この資料のみから当時の「一般常識」など窺い知る事など出来ませんし、先生のおっしゃる「一般常識」に合ってもいません。「一般常識」なるものは相当数の資料の分析無くしては推測すら不可能です。江橋先生が主張の根拠とする諸資料の公開を切に望む次第です。
次に、江橋先生の言われる「当時の知識人」の「一般常識」とは少し性格が異りますが、江戸初期に発せられた御触書を見て頂きましょう。
アラ大変!!! 江橋先生の論理によれば「準博奕の扱いである」はずの「かるた」を、「主犯格の骰子賭博」の前に持って来てしまいました。
前半が御触の本文で、慶安二年のものと同じく“カルタ・サイコロ・諸勝負”の順番に成っています。「覚」以下の部分は、町役人に対して、町内に博奕を打つ「いたずら者」は一人もいない事を確認し報告を求めた“報告書”の文面の雛形です。ここでは“サイコロ・カルタ・諸勝負”の順番に成っています。一つの御触書の文面の中でさえカルタとサイコロの順番は統一されていません。
これらの例を見る限り、幕府のお膝下である江戸の為政者達は「主犯格」であるサイコロ博奕と、「準博奕」である筈のカルタ博奕の記述順には無頓着だった様です。又、他の町触れも含めて“双六”について言及したものを知りません(諸藩の藩法には見られますが)。どうやらこれらのお触れを出した幕閣や町奉行所には、賭博に対する「専門的な知見」や「一般常識」を持った人物は居なかった様です。まあ、当時にせよ現代にせよ、為政者や役人は世間の一般常識に疎かったのでしょうけど。
取材した時期の取材した地域で特殊にカルタ賭博が骰子博奕を上回るほどに盛んであったのだろうか。それとも、貝原にとってはカブ系のカルタ賭博の悪印象が骰子博奕を上回るほどに強かったのであろうか。
「取材した時期の取材した地域で特殊にカルタ賭博が骰子博奕を上回るほどに盛んであったのだろうか」との事ですが、「盛ん」とは愛好者の数が多い事だとすれば、当方の印象では江戸時代の殆どの時期、地域においても、サイコロ賭博よりもカルタ賭博の愛好者の方が多かった、つまり「盛ん」で有ったであろうと云う印象を持っています。サイコロ賭博の常習者が一部の階層に限られていたのに対し、“よみ”や“めくり”等のカルタ賭博(少額の賭けの場合も含めて)が幅広い階層に愛好されていた事は、当時の文芸資料や絵画資料に取り上げられている頻度から見ても間違い無いと考えます。少なくとも「カルタ賭博が骰子博奕を上回るほどに盛ん」なのが「特殊」な状況だとは思われません。
執中堂西山は後の部分で「就中、さい哥るたの二品ハ、下品の悪勝負」と書いており、つまり“さい=サイコロ博奕”と“哥るた=カルタ博奕”の二種が悪質な博奕の双璧だと認識していた事が解ります。更にサイコロ博奕について「勝負彼(かの)かるたに倍し、過分のかちまけありと云へり。」と、カルタよりもサイコロ博奕の方が、掛け金が高額になる分悪質だという認識を示しています。にも拘らず、何故最初にカルタの記述から始めたのでしょうか。たしかに不思議では有ります。思うに、いみじくも先生のおっしゃる様に「カルタ賭博の悪印象が骰子博奕を上回るほどに強かった」からだと考えるのが自然でしょう。表現を少し変えるならば、カルタ賭博が世間に与える悪影響が、サイコロ博奕を上回るほどに強いと感じていたからと云う事です。
お馴染みの資料に再度登場願いましょう。
「かるたは博奕の第一なり」と有ります。勿論当時サイコロ博奕も盛んであったでしょうが、一般庶民にとってはカルタこそが最も身近な賭博であり、「博奕の第一」と認識されていた事が窺われます。同じ様に執中堂西山の目にも、一部の玄人や無頼漢に限られていたサイコロ博奕よりも、世間の幅広い階層に浸透していたカルタこそが最も憂うべき博奕と映っていた、つまり悪印象が強かったが為に先ず最初にカルタ博奕を挙げたものと考えられます。
或いは単に、執中堂西山はカルタ博奕については良く知っていたが、サイコロ博奕については殆ど知らなかったのでカルタから始めたと云う、身も蓋も無い解釈も成り立ちます。案外これが正解だったりするかも知れません。
次に、いずれにせよカルタ博奕を博奕の代表例として述べるのであれば、真っ先にカブ系の「かう」や「おいてう」を挙げるのには納得がいくが、それに次いで「よみ」や「あはせ」も博奕の類型として並べて取り上げているところを見ると疑問が起る。「読み」や「合せ」は、通常は博奕の一種とまでは観念されておらず、刑罰も博奕のように死罪、遠島、追放などではなく、敲(たた)き、重敲き程度の軽罪でしかないものを、なぜ重罪の博奕の一種としてここに書いてしまったのか。
江橋先生は少し前の部分で、カルタ賭博に関して「罪の程度も軽度で重罪の博奕には含まれない準博奕の扱いである。もっとも、カルタの遊技法の中で「カウ」などのカブ系の賭博は博奕並みに悪質なものと理解されていた」と書かれていましたが、それと同じ事をおっしゃっている様です。但し今度は「読み」や「合せ」は「準博奕」ですら無く「通常は博奕の一種とまでは観念されておらず」とされるのでチョット混乱します。少なくとも当時の「読み」が、往々にして金銭を賭けて遊ばれていた事は先生もご存じな筈です。「博奕の一種」で無いならば、一体如何なる罪状で「敲き、重敲き」の刑に処されたのでしょうか?
江橋先生は、賭博の種類によって刑の軽重が有ったとおしゃりたいのでしょう。具体的にはサイコロ賭博やカルタの「かう」系技法は「死罪、遠島、追放」に該当する「重罪の博奕」であり、「読み」や「合せ」は一段軽い刑罰である「敲き、重敲き」に当たる「準博奕」だとお考えの様ですが、又してもその根拠が示されていませんので、そのまま鵜呑みにする事は出来ません。
江戸初期の御触書でカルタに対する禁令が度々出されていますが、当方の知る限りでは技法の種類によって刑の軽重を別ける規定の有るものを知りません。まあ、常識的に考えて“「かう」は厳罰だけど「読み」や「合せ」なら少し刑は軽いよ”などというお達しが出されるとは思われませんので、無くて当然でしょう。諸藩の藩法に関しては未調査ですが、少なくとも幕府による御触書にはその様な規定は無いと考えていますが、どうなのでしょうか。
恐らく江橋先生は、当時の判例(裁判記録)を根拠とされているのだろうと推測しますが、当方不勉強の為「かう」系技法によって「死罪、遠島、追放」に処された具体的な例も、「読み」や「合せ」が「敲き、重敲き」に処された例も知りません。
尚、幕府の御膝下である江戸の町奉行所で「敲き」が正式に刑罰の体系に組み入れられたのは享保五年(1720)が最初だと認識していましたが、実際はそれ以前から有ったのでしょうか。先生は『教訓世諦鑑』を宝永八年(1711)刊だという前提で論じらていますので、宝永年間以前に、軽い賭博に「敲き、重敲き」の刑が課された事例をご存じなのでしたら、これについても是非ともお教え願いたいものです。
結局この部分の内容に関しては、当方には江橋先生の豊富な知識に対抗出来るだけの知識が有りませんので、先生の主張に対して断固否定する材料も、積極的に肯定する材料も持ち合わせておりません。しかし、自分の不勉強を棚に上げて言わせて頂けば、具体的な根拠となる資料を示して頂かない事には、妥当な批判だと認める事は出来ません。
もう一点、別の観点から反論させて頂きます。「読み」や「合せ」を「なぜ重罪の博奕の一種としてここに書いてしまったのか」という批判点は、江橋先生の誤解に過ぎません。
先生は冒頭の一丁分しかお読みになっていないので、三種のカルタ技法と、続くサイコロ博奕の記述のみを基に考察された為の勘違いかも知れませんが、仮に当時「読み」や「合せ」は「重罪の博奕」と観念されていなかったにせよ、そもそも執中堂西山は『教訓世諦鑑』の「博奕」の項で、「重罪の博奕」についてのみを論じている訳では有りません。その後の部分で“なんこ”“双六”“おりは”“宝引”“三笠付”“だいいち”等、各種の賭博に幅広く言及した上で、「過分のかちまけ」の有る悪質なサイコロ賭博から「壱銭弐銭のよミ、かるたも、五もく壱銭の、かけ碁」といったほんの慰み程度の小バクチに至る迄、なにがしかの金銭を賭ければ全て賭博に外ならないと断罪しています。執中堂西山は「重罪の博奕」のみを論じている訳では無く、自身の知っている賭博全般を例に挙げて論じているのですから、そこに比較的軽い賭博の「読み」や「合せ」が書かれていても何等不自然な記述では有りません。先生も『教訓世諦鑑』全体を読まれれば納得頂けると思います。
当時としてもきわめて例外的な記述の仕方であり、カルタ遊技の実体に関する知識や、博奕を論じるのに必要な法制史的な素養も十分でなかったのではないかと疑わせるものがある。
今述べた通り「読み」や「合せ」を「重罪の博奕の一種としてここに書いてしまった」事が「きわめて例外的な記述の仕方」であるとして問題視するのは、全くの誤解です。更に言わせて頂けば、これを“例外的”だとする根拠となる、当時の“一般的”な記述例を示して頂きたいものです。
執中堂西山の「カルタ遊技の実体に関する知識」に関しては、この後個々の技法の説明の部分で述べる様に、他のカルタ資料との間に矛盾や、明らかな齟齬は無く、基本的には信用出来るものと考えます。
「博奕を論じるのに必要な法制史的な素養も十分でなかったのではないかと疑わせるものがある。」との事ですが、そりゃあ現代の研究水準での「法制史的な素養」を十分にお持ちの江橋先生から見れば、著者の素養が物足りないと感じるのは当然でしょうし、当方から見ても彼がその手の素養を持っていた様には見えません。しかし、賭博の弊害について論じようとする者にとって「法制史的な素養」が必ずしも必須の条件だとは思えませんし、少なくとも資料の信頼性とは全く関係は有りません。
執中堂西山は博奕の害悪を説く目的の為に、自身の見聞した範囲の賭博技法の種類と概略を簡潔に説明しただけであり、博奕の法制史などを論じる気などは毛頭有りません。「法制史的な素養」などを持ち出して難癖を付けられては、彼としてはさぞかし心外な事でしょう。
江橋先生はここ迄(この後もですが)の立論の根拠として、唯一『長曾我部元親式目』に触れた以外には、見事な迄に一点たりとも資料根拠を示さずに論を進められて来ました。全て先生ご自身の“認識”という、外部からは検証不可能なものを根拠とする立論です。何故先生がこれ程迄かたくなに根拠資料を秘匿しようとされるのか、全く理解に苦しみます。先生はそれで客観的な史料批判として成り立っているとお考えなのでしょうか。
江橋先生の主張には資料根拠を示されないものが多い事は今迄も度々指摘してきました。当方は可能な限り資料根拠を示す方針を採っておりますし、見出した全ての資料を「江戸カルタアーカイブ」にて随時公開しています。別に自分の発見をひけらかしたい訳では無く(少しは有りますが)、カルタ研究の未来を担う研究者の一助に成ればと云う思いによるものです。
勿論、当方の様なアマチュアとは違い、江橋先生は現役のプロ研究者ですので自ら発掘した新資料は言わば大事な飯の種であり、その全てを公開せよなどと言う積りは有りません。しかし、学術論文や学術的な書籍での主張には根拠となる資料の明示が不可欠なのは言う迄も有りませんし、例えネット上での啓蒙的な文章であるにせよ、未来の研究者の為にも少なくともソースに繋がる最低限の情報だけでも示して頂きたいと願います。そうする事によって『日本かるた文化館』が今以上に価値有るものに成ると考えますが、如何でしょうか?
江橋先生によるここ迄の論点を要約すると、その中核は『教訓世諦鑑』の記述の構成が「当時の知識人」の博奕に対する「一般常識」と合っていない、或いは「当時としてもきわめて例外的な記述」と云うものです。史料批判の方法論としては正当なものかも知れませんが、そう主張する為には当時の「一般常識」なるものを示す資料の提示が必要不可欠です。それ無くしては全く成り立たない論法であり、そもそも学問的な論争の争点にすら成り得ないと考えます。勿論先生が論拠とする諸資料を公開して下さるならば、当方としても真摯に再検討させて頂く積りです。
当方も不勉強の為、直接的な反証と成る様な具体的な証拠を十分に示せていないかも知れませんが、それでも最低限の根拠資料に基づいて論じている積りです。対して江橋先生の主張はどれも明らかに証拠不十分です。よって“疑わしきは罰せず”の原則に従って却下されるべきだと考えます。
次に、カルタ博奕の「品」(種類)の紹介の仕方であるが、各々の種類の遊技法の説明がどれも簡単過ぎて、記述の意味を一義的に読み取ることが難しく、どういう遊技法であったのかが分かりにくい。
次なる批判点は「記述の意味を一義的に読み取ることが難し」いと云う点です。まあ、これには基本的に同意せざるを得ませんが、「簡単過ぎ」「分かりにくい」という理由で資料としての信頼性が低いと見做すのは全く論外です。この点に対する当方の基本的な考えを説明しておきます。
執中堂西山が『教訓世諦鑑』を著した目的は賭博の害悪を説く為であり、間違ってもカルタ賭博の愛好者を増やす為の“指南書”を書こうとした訳では有りません。従って、読者にカルタ競技のルールを事細かに伝授する必要は有りませんし、勿論未来の研究者からイチャモンを付けられない様に詳細に説明をしようという意志など有る筈は有りません。あくまでも同時代の平均的な読者に向けて、彼等が当時流行していたカルタの遊技法をそこそこ知っているであろうという前提の上で、必要最小限の説明をしただけの事です。「簡単過ぎ」「分かりにくい」事を批判の主たる論点にするのは全くの見当外れです。
『教訓世諦鑑』の記述を「簡単過ぎ」とするならば、そもそも江戸カルタに関する資料の殆どは「簡単過ぎ」どころのレベルでは無く、言わば断片の様なものと言えます。当方の印象では総数1100余点のカルタ関係資料の内で、遊技法についてある程度まとまった情報を得られる記述と言えるものは、甘く見てもせいぜい10数点程に過ぎません。つまり全体の約1%程度であり、残りの99%は「簡単過ぎ」か、もしくはそれ未満でしょう。
例えば、江戸カルタに関する重要な情報源である古川柳や雑俳資料等は、まさしく“断片”に外なりません。その中には現代の我々には句意がさっぱり判らないものが山ほど有りますが、それらは多数の応募作品の中から撰者が選んだ入選作であり、少なくとも撰者や当時の読者の多くには理解可能だったものです。現代の我々の感覚で、記述が簡単過ぎて理解不能と感じるのは記述者の落度では無く、読み取る側の能力不足の為に外なりません。いかに断片的な記述にせよ、そこから有用な情報を読み取り、再構築をして全体像を明らかにする事こそ研究者のなすべき仕事であり、責任だと考えます。
江戸カルタの遊技法について最も詳しく記された資料は『博奕仕方』(特に「めくり博奕仕方」の項)でしょう。それに次ぐものとしてはやはり『雍州府志』でしょうか。しかしそれとて、特に“合せ”の説明などは「記述の意味を一義的に読み取ることが難し」い点では『教訓世諦鑑』と五十歩百歩か、寧ろ『教訓世諦鑑』の方がより具体的であり、理解し易いと思われます。『教訓世諦鑑』の記述が「説明がどれも簡単過ぎて、記述の意味を一義的に読み取ることが難しく、どういう遊技法であったのかが分かりにくい」と云う理由で切り捨てるならば、江橋先生は一体どの様な資料に基づいてカルタの研究を為されるというのでしょうか?
江橋先生は大好きな『雍州府志』に対しては、記述の不十分な部分を「黒川の記載ミス」と認めながらも不足部分を「忖度」し、ご自身の「推測」によって補った上で「黒川の説明が多少端折った文章になっているのは不思議ではない。黒川に対しては、よくぞここまで記録を残してくださったという感謝の気持ちはあるが、欠けている部分のあることを責める気持ちは全くない。」という評価を下されます。一方、『教訓世諦鑑』に「欠けている部分のあること」は絶対に許せない様です。
当方は執中堂西山に対しても「よくぞここまで記録を残してくださったという感謝の気持ち」を持っています。その他のほんの断片に過ぎない大多数の資料にしても、その一つ一つには何等かの意味が有ると考えますし、それらの記録を残して下さった全ての著述者に対しても感謝こそすれ、一点たりとて価値の無い資料として切り捨てる事など絶対に出来ません。
江橋先生はこの「簡単過ぎ」「分かりにくい」という論点を、この後の個別の技法説明に対する部分でもしつこく繰り返されますので、当方もその都度しつこく反論させて頂きます。
この後、江橋先生は個々の技法説明に対する批判に移ります。
(2)“長半カルタ(仮称)”について
半のかずに、三五七九と、あたるを勝とし、二四六八を、皆まけとす。是ハ哥留多三枚をもつて、其長と半との印を見る。爰において、かう、おいてう、など云へる、色々の名あり。
まず冒頭のカブ系の遊技法の説明は、三枚の札の丁半で勝負が決まるとしているが、それは、参加者の各人に三枚の札を配分し、各人ごとに親との勝負をする遊技法を説明したのか、親の手元に三枚を開いて、それが半なら親の勝ち、丁なら親の負けで参加者の勝ちとする遊技法なのか、分からない。三枚の札からどのようにして丁半を判定するのかも書かれていないので分からない。常識的には三枚の札の「紋標数」を足して奇数か偶数かを判断するのであるが、それでよいのだろうか。
先ず、何故これが「カブ系の遊技法」なのでしょうか? “かう(カブ)”系技法の基本原理は、二枚から三枚の札の数字を合算し、合計の一の位が九を最高とするものであり、ここに記されている技法とは勝利条件が全く異なります。恐らく先生は「カブ系の遊技法」と手続きが似ており、博奕色が強い遊技法であろうと考えて「カブ系の遊技法」と記されたと想像しますが、分類としてはちょっと大雑把過ぎると感じます。これは「カブ系の遊技法」とは勝利条件の異なる、サイコロの長半賭博に似たカルタ技法の説明であり、“長半カルタ(仮称)”と命名しました。
江橋先生の「参加者の各人に三枚の札を配分し、各人ごとに親との勝負をする遊技法」と云う解釈は、当方が前稿で示した“試案②”と同じですね。三枚の札の数を「足して奇数か偶数かを判断する」と云う「常識的」な判断には勿論同意致します。
文章は、出目が半であれば常に勝ちで、丁があれば常に負けというように読める。これでは丁半博奕のもっとも基本的なルールに反していて博奕にならない。
そう読めますかね? たしかに「半のかずに」を無視すればその様に読み取る事も可能でしょうが、原文に忠実に読めばそうは読めないでしょう。
だがこれは貝原の書き方が悪いのであって、「半(はん)のかずに、三五七九と、あたるを勝(かち)とし、二四六八を、皆(みな)まけとす」というのは、親の三枚の札の合計が「半のかず」であったときには、子で「三」「五」「七」「九」と半の側に賭けて「あたる」者を「勝(かち)とし」、いっぽう、三枚の合計が「二」「四」「六」「八」だと長(丁)に賭けた子は「皆(みな)まけとす」なのであろう。これは骰子を用いた丁半賭博をそのままカルタで行っていることになるのであるから、成り立たない話ではない。
この文の解釈として成り立ちますね。当方が前稿で示した“試案①”と同じです。
ところで言葉尻を捉える様ですが、現代の我々から見て曖昧で分かりにくいと感じられる記述に対して、それは著者の「書き方が悪いのであって」という捉え方は如何なものでしょうか。勿論現代でもそうである様に、中には本当に「書き方が悪い」ものも有るでしょうが、基本的には同時代の読者には普通に理解される書き方だと考えるべきでしょう。現代人の感覚で理解し辛いと感じられる記述の多くは「書き方が悪い」のでは無く、読み取る側の読解力が未熟なのだと考えます。
だが、この遊技法の名称として記載されている「かう」や「おいてう」は丁半の賭博ではなく別物である。
当方は前稿で、ここでの「かう」や「おいてう」は遊技法の名称では無く、数字を表す符丁と考えるべきだと論じました。まあ、確かに別物に違い有りません。
「かう」がポルトガル語の「九」に由来し、「おいてう」が「八」に由来するように、
ちょっと待った~!!! 話の途中ではありますが、素通りする事が出来ない重大な疑問が有りますので、一旦中断させて頂きます。
江橋先生は『かるた』の中でも次の様に書かれていました。
問題は「カブ」、当時の呼称では「カウ」である。これは九が最上の数で八がそれに続くのであるが、数の呼称が九は「カブ」で八は「オイチョウ」で、そこからゲームの呼称も「カブ」とか「オイチョカブ」になった。この呼称は、各々スペイン語の九であるカブ、八であるオイチョウに由来するので、江橋崇『かるた(ものと人間の文化史 173)』
法政大学出版局 2015年 p.32
いつの間にか“スペイン語”が“ポルトガル語”に変わっている事などは大した問題では有りません。重大な問題はスペイン語にせよポルトガル語にせよ「九であるカブ、八であるオイチョウに由来する」とする根拠が不明だという点です。
当方がこの問題に対して最初に疑問を抱いたのは、かれこれ20年程前の事です。当方がカルタ研究の世界に足を踏み入れる切っ掛けとなった、松田道弘氏の名著『トランプものがたり』に次の様な記述が有りました。
追丁株(追帳株とも書く)の語源は知らなくても、カブを日本語だと信じこんでいる人も多いと思います。日本の賭博用語には、ポルトガル語、スペイン語がふんだんに流れこんでいます。賭博には種族保存本能に似た一種奇妙な保守性があります。
オイチョウはスペイン語で八、カブは九のことです。松田道弘『トランプものがたり』
岩波新書 1979年 pp..43-44
当時、念の為にスペイン語とポルトガル語の“八”“九”を調べてみましたらビックリです。確かに“八”はスペイン語では“ocho”ポルトガル語では“oito”であり、何れも“おいちょう”に訛ったとしても不思議では有りませんし、寧ろそれが語源だとしか考えられません。しかし“九”はスペイン語では“nueve”ポルトガル語では“nove”であり、どちらも“かう”とは似ても似つかない発音です。どういう事?
疑問を抱きながらも“多分松田先生の勘違いかな?”位に軽く考えていたのですが、何と江橋先生までもが同じ主張をされているでは有りませんか! もう一度、今度は古語や方言等も気に掛けて調べ直したのですが・・・やはり分りませんでした。
ちなみに『日本国語大辞典』では“カウ・オイチョー【迦烏追重】”という見出し語を採用しているのですが、その語釈の中で「オイチョーは (スペイン) ocho で「八」の意」としていますが、“カウ”の語源については触れていません。
如何なる根拠で“カウ”の語源が、スペイン語やポルトガル語の「九」だとおっしゃるのでしょうか。この問題は“解釈”の問題では無く、カルタ史研究に関する基礎認識に係わる重大な問題です。博識な江橋先生の事ですので、当方など考えも及ばない根拠を持ってのご主張ならば、後学の為に是非ともご教示頂きたい。或いは、もしも松田道弘氏の記述を検証無しに踏襲された事による誤認ならば、躊躇せずハッキリと訂正して頂きたいと思います。
「じゃあ、ポルトガル語やスペイン語で無いならば“かう”の語源は何なのさ?」という当然の疑問に対して、先手を打って簡単に私案を示しておきましょう。
話を戻しましょう。
「かう」がポルトガル語の「九」に由来し、「おいてう」が「八」に由来するように、「紋標数」の合計が「九」ないし「八」であるかそれに一番近い者(但し十はブタでゼロ扱い、十一は一扱い、以下省略)を勝ちとする遊技である。ただし、「かう」は古くは「カウオイチョウ」と呼ばれ、後に「オイチョカブ」と呼ばれることはあったが、「カブ」と別に「オイチョウ」と言う遊技名のものが成立したのではない。
この説明の中でもう一箇所、どうしても気になって素通り出来ない部分が有ります。又しても話が本筋から逸れてしまいますが、どうかご勘弁下さい。
それは「「かう」は古くは「カウオイチョウ」と呼ばれ、後に「オイチョカブ」と呼ばれることはあった」という部分の「カウオイチョウ」と「オイチョカブ」の語に関してです。書かれている事に大きな間違いは有りませんが、厳密に言うと不正確であり、読者に誤解を招く恐れが有ると思います。
先ずは「カウオイチョウ」の語ですが、これは江戸初期の『浮世物語』に見られる「迦烏追重」の事でしょう。先生ご自身は出典を示されていませんが、この資料に拠っているのは明らかです。
当方もこの「迦烏追重(かうおいちょう)」が、“かう”系技法の古称である可能性は高いと考えます。しかし、管見ではこれが“かうおいちょう”の最初にして唯一の用例であり、他には見当たりません。ちなみに『日本国語大辞典』の“カウ・オイチョー【迦烏追重】”の項でも、用例として『浮世物語』のみを記載しています。『日本国語大辞典』の用例は最初に一番古いものを掲載し、原則として複数の用例を年代順に載せていますので、つまり『日本国語大辞典』の編集者も“カウ・オイチョー”の用例を『浮世物語』以外には見つけられなかった事を意味します。
『浮世物語』の「迦烏追重(かうおいちょう)」は、確かに技法名の様に見えますが、同書には「重迦烏」という記述(二箇所)も有り、これも又技法名の様にも見えます。更に、ほぼ同時代の『讃嘲記時之大皷』には“かう”のみで登場しています。
『浮世物語』に僅か数年遅れているだけで、ほぼ同時代と言っても良いでしょう。従って“かうおいちょう”の呼称が、“かう”に先んじて使われていたと迄は言い切れません。ですので「「かう」は古くは「カウオイチョウ」と呼ばれ」たという記述は、これらの名称に先後関係が有ったと云う事では無く、“かう系技法”の古い呼び名に“かうおいちょう”が有ったと云う程度に受け取って頂きたいと思います。
もう一点、“かう”が「後に「オイチョカブ」と呼ばれることはあった」と云う記述も誤解されそうですので補足説明させて頂きます。
「オイチョカブ」は、今日に伝わっている幾つかの“かう系技法”の中で最も知名度が高く、広範囲で行われている技法でしょう。但し記録に登場するのは恐らく近代以降の事であり、管見では尾佐竹猛の『賭博と掏摸の研究』(大正十四年刊)の第七章「加留多賭博の三大系統」に載る、カルタ技法の一覧を示した表中に「追丁カブ」と有るのが最も古いものです。丁寧に探せばもう少し古いものも見つかると思いますが、江戸期迄遡るのは難しい様に思えます。当方の知る限り江戸期の資料にはその名は見られませんし、「オイチョカブ」の特徴的な初期レイアウトに関する記述も、それを描いた絵画資料も見当たりません。「オイチョカブ」は江戸期の“かう”とはかなり形態が異なっています。“かう系技法”の子孫であるのは間違い有りませんが、直系の子孫では無く、傍系と捉えるべきでしょう。
先生は以前、『浮世物語』の「迦烏追重」に関連して、次の様に書かれていました。
「迦烏追重」は「迦烏」と「追重」ではなく、「迦烏追重」、つまり後世には「オイチョカブ」と呼ばれた遊技法のことであり江橋崇『かるた(ものと人間の文化史 173)』
法政大学出版局 2015年 p.184
ここでは「後世には「オイチョカブ」と呼ばれた遊技法のこと」と、「オイチョカブ」は江戸期の“かう”の呼び名が変わったものだという認識を示されていますが、当方としては、江橋先生の誤認であると考えます。
「「かう」は古くは「カウオイチョウ」と呼ばれ」、「後に「オイチョカブ」と呼ばれることはあった」、「後世には「オイチョカブ」と呼ばれた遊技法」等の記述を併せ見る限り、同一の技法の名称が「カウオイチョウ」→「かう」→「オイチョカブ」と変化した様に読めます。江橋先生がその様に認識されているのかどうかは判りませんが、少なくともその様に受け止められる書き方に成っているのは間違い有りません、しかし、実際はそんな単純な流れでは有りません。読者の皆様には誤解をされぬ様に願います。
寄り道が長く成りましたが、今度こそ話を戻しましょう。
先生がおっしゃりたいのは、“かう系技法”の中には「カウオイチョウ」や「オイチョカブ」と呼ばれた例は有るが、“おいちょう”という名称の技法は無い、という意味でしたらこれには同意します。おっしゃる通り、管見でも“おいちょう”単独で遊技法の名称として用いられた例は思い当たりません。
続きを見ましょう。
この文章では、「かう」と「おいてう」の間に句点が打たれているので別種の遊技として読んだが、奇妙である。貝原はこの点でも博奕の実際を知らない様である。
何が「奇妙である」のか? 何故それで「博奕の実際を知らない様」だと言えるのか? 確かに「かう」と「おいてう」との間に読点(句点ではありません。もっとも当時の句点と読点の区別は曖昧ではありますが)が有るのですから、当然それぞれを独立した語として読むべきでしょう。先生はこれを“かう”と“おいちょう”という二通りの技法名が有ると云う意味と解釈され、実際には“おいちょう”という遊技法など無いのだから「奇妙である」。それは「博奕の実際を知らない」からだと言いたいのでしょうが、勿論この主張には同意出来ません。
先生のおっしゃる通り、当方も“おいちょう”という遊技法の存在は知りません。江戸期の文献に見られる“おいちょう”は、殆どの場合“かう”系技法において“8”の数を表す符丁としてのみ使われている語です。従ってここでの“おいちょう”も“8”を表す符丁である可能性が高いと考えるべきでしょう。尚、併記されている“かう”には技法名と符丁と両方の用法が有りますが、ここでは“おいちょう”と同じく“9”を表す符丁としての用法と考えれば、スッキリと理解出来ます。又、“かう”“おいちょう”を符丁だと考えれば、「爰において、かう、おいてう、など云へる、色々の名あり。」が文章として自然に解釈出来る事を前稿で示していますのでご参照下さい。つまり、この部分の“かう”と“おいちょう”を数の符丁だと考えれば、この文章に「奇妙」な点など全く有りはしません。
江橋先生は“おいちょう”という名の技法が存在しない事を認識されています。それならば、併記されている“かう”も含めて技法名では無く、他の意味である可能性も考えるべきでしょう。しかし先生は「奇妙である」と感じても、自分の前提の方が間違っている可能性は考えもされない様で、著者は当時の「博奕の実際を知らない様である」と一方的に責任をなすり付けて解決されます。先生は凡そ三百年前の「博奕の実際」を、同時代の著者よりも余程ご存じの様で全く恐れ入るしかありません。浅学の当方は、当時の「博奕の実際」など未だに解らない事だらけです。
また、「カブ」系の遊技では、参加者は二枚の札を配分された段階で、三枚目を要求するかしないかの選択権を持っている。貝原が説明している様に例外なく三枚で勝負する遊技法ではない。
全く的外れな論点による批判です。前にも言いましたが、ここに記されているのは“かう”系の遊技では無く、全く別の原理による遊技です。従って“かう”と同じ手続きであらねばならぬ必然性は有りません。先生は最初に「カブ系の遊技法」と云う雑な分類をしてしまった為、この様な論理が成り立つと勘違いされたものと想像します。
先生ご自身、前の部分で「「かう」や「おいてう」は丁半の賭博ではなく別物である。」と書かれ、又この後の部分で「貝原は勘違いして名称と別種の丁半博奕を」云々とおっしゃっています。“長半カルタ(仮称)”が“かう系技法”と「別物」「別種」のものと認識されているにも拘わらず、ここで“かう系技法”の手続きとの相違点を問題視されるのは、明らかに論理的に破綻していると言わざるを得ません。江橋先生は攻撃のネタを探すのに熱心のあまり、冷静な批判力を逸している様に感じられます。
ところで、全ての“かう(カブ)”系の技法が最初に二枚の札を配り、三枚目の取得は任意であり「例外なく三枚で勝負する遊技法ではない」と云う前提も、もう少し慎重に検討しておくべきでしょう。
確かに現在良く知られているカブ系技法では三枚目を取るか取らないかは任意ですし、江戸期の資料でも概ねその様な印象を持ってます。しかし、実は江戸期の“かう系技法”の中に「例外なく三枚で勝負する遊技法」だと解釈し得る資料が一点有りますのでご紹介しておきます。
ここに記されている技法の名称は「三枚のかう」です。元禄八年以前(-1695)刊の『やく者絵づくし』に「ひねつてあそべ三まひがう」と有るのも同じ技法と思われます。これが、単に“三枚”と表記されている技法と同一のものであるのかの判断は、今は保留とさせて頂きます。
札をオープンする場面の描写ですが、「はた(子)」の一人目は「うんすん(1点)」です。続く「二番目はふだ三寸より高はない」の解釈が難しいですね。二人目が「三寸(3点)」とも考えられますがどうもスッキリしません。或いは「二番目はふだ」で区切り、「ふだ」を“ぶた(=0点)”と読めなくも有りません。などと書くと、「“ふだ”が“ぶた”と読めるなどとメチャクチャな読解が有るか~!!!」 というお怒りの声が聞こえて来そうですが、真にメチャクチャなのは、江戸時代に於ける濁点(゛)や半濁点(゜)の用法の方なのです。本来濁点が打たれるべき場所に正しく打たれている方が少なく、寧ろ濁点が省かれている方が普通ですので、読む方が文脈から想像して補うしか無いのです。例えば、北海道の幹線道路に道東道(どうとうどう)が有りますが、江戸時代ならば“とうとうとう”(或いは“とう/\/\”)と書かれたかも知れません。“とうとうとう”単独では意味を理解するのは困難ですが、「北海道地方は大雪の為“とうとうとう”は通行止めになっています。」という文脈の中ならば“道東道”が思い浮かぶでしょう。同様に、江戸期の文献でも或る程度文脈を読み取れる様に成れば、さほど不便には感じなく成るものです。
更には、本来濁点が無い筈の箇所に打たれていたり、濁点と半濁点がアベコベになっていたりする、奇妙キテレツな例さえ稀では有りません。現代の感覚では理解しづらいのですが、まあ、そういうものだと納得するしかありません。
という訳で、“ふだ=ぶた”という解釈も有り得ると強引に考えてみたのですが、やはりちょっと苦しいかな~ まあ、何れにせよ子の内の最高は3点です。
《追記》
もう少し早く気が付いていれば、こんなおバカな事を書かずに済んだのですが、後の祭りです。
東京藝術大学附属図書館に所蔵されている『傾城暁の鐘』の原本がネット公開されている事に気付きました。原本を見れば謎は簡単に解けました。問題の箇所の原文は「二番目ハぶた三寸より高ハない」でした。濁点(゛)は明らかに「た」では無く「ふ」に付いており、校訂者の読み間違いだと判明しました。二人目の手は“ぶた(=0点)”です。
一方、親の札は一枚目が「切(10点=0点)」、二枚目が「青八(8点)」、この時点で「おいてう(おいちょう)」確定ですので、三枚目の札が任意ならばもう一枚引くと云う選択は有り得ません。ところが何故か三枚目の札を持っており、それをソロソロと見て行くと上部に大きな円形が見えて来たので“釈迦十(10点)”の後光だと思い勝利を確信したが、全部を開けると「たいこの二(2点)」で、結果「ぶたつた(0点に成った)」という落ちです。
これを見る限り、競技者が必ず三枚の札を引くというルールであった様に見えます。ここで描写されている遊技が“かう系技法”であるのは疑い様が有りませんし、「三枚のかう」という技法名からも、必ず三枚で行うタイプの“かう系技法”で有ろうと云う推測も成り立ちます。勿論『けいせい暁の鐘』は創作物であり、現実を正確に描写したものであるのか疑問ですし、何しろ現状では唯一の例ですので無視するのは簡単です。しかしもしも、もう一点同様の資料が見つかれば、もう無視は出来ませんし、更にもう一点見つかりでもしたならば、信憑性はかなり高いと評価出来ます。
貝原は勘違いして名称と別種の丁半博奕を、それも実際には成立不可能な形で説明しているのに、そのことに自分で気付いていない。
前に先生は、ご自身が示された読解について「成り立たない話ではない」とされていましたが、突然「実際には成立不可能な形で説明している」と、真逆な事を言われます。何が「成立不可能」なのでしょうか? “長半カルタ(仮称)”自体が、技法として「成立不可能」な訳では決して有りませんし、執中堂西山の説明が「成立不可能な形」だとも思えないのですが?
以上要するに、貝原の説明では、当時の社会でのカルタ札を使った丁半博奕の実態は分からないし、そもそも説明されている博奕が本当にあったのかも疑わしい。
おっしゃる通り、この文章のみからは「当時の社会でのカルタ札を使った丁半博奕の実態は分からない」のは事実ですが、それは研究者側の問題であり、著者の責任では有りません。少なくとも資料の信頼性とは全く関係有りません。
それにしても江橋先生は遂に「本当にあったのかも疑わしい」と、“長半カルタ(仮称)”の存在自体を否定して、亡き者にしようとされます。まあ、存在に疑問を抱かれるのは自由ですが、確たる証拠も無しに「疑わしい」と云うだけで罰するならば、それは冤罪である可能性が高いと言わざるを得ません。
そもそも“長半カルタ(仮称)”は存在しなかったという仮説を証明する事は出来ません。如何なる論証を用いようとも、“存在しなかった”事を証明するのは、原理的に不可能である事はご理解頂けますよね。せいぜい“存在した”事を裏付ける資料が全く見つからなければ、暫定的に“存在しなかった”蓋然性が高まると云う事に過ぎません。
一方、“長半カルタ(仮称)”は存在したという仮説は、それを裏付ける信頼の置ける資料根拠や、強力な状況証拠(出来れば複数)が示せれば証明が可能です。当方は前稿で『浪華獅子』の「長班」が“長半カルタ(仮称)”である可能性を論じました。しかし自分で言うのも何ですが、さほど説得力の有る論証とは言えません。両書が共に大坂版だという共通点は有るものの、時代的には約50年隔たっている事もあり、強力な傍証と言うには程遠いものです。又、『文政三辰年御渡』の御仕置例によって、カルタを使った長半賭博が確実に存在した事を示しましたが、『教訓世諦鑑』と時代的には100年隔たった、しかも北関東の事例ですので、直接的な繋がりを考えるのは難しいでしょう。
ところでこれに関連して、最近ちょっと気になる記述を見つけました。一つ目は宮武外骨の『賭博史』(大正十二年刊)からです。
此骨牌を丁半バクチに使用する事もある(花カルタは月数の奇偶を丁半に分つ)が、それは稀で、丁半は采コロでなくば面白味がないと本職の者は云って居る、廢姓外骨(宮武外骨) 『賭博史』
半狂堂 大正十二年
これは正に“長半カルタ(仮称)”そのものです。又、ほぼ同時代の尾佐竹猛による『賭博と掏摸の研究』の第九章「賽と加留多」にも同様の記述が有りました。
現今宮崎県の一部に行わるる花合せ丁半は賽が加留多に変った著しい例である。尾佐竹猛 『賭博と掏摸の研究』
総葉社書店 大正十四年
前後の文脈から“花合せ丁半”は花札を使う丁半賭博、つまり“長半カルタ(仮称)”と同種の技法だと推測されます。“花合せ丁半”は大正時代の宮崎県の一部で確認された技法との事ですので、これも『教訓世諦鑑』の時代の大坂で観察された“長半カルタ(仮称)”と直接的な繋がりは無いでしょう。しかし、宮武外骨や尾佐竹猛によるこれらの証言から、大正時代末期にカルタ(花札を含む)を使った長半賭博が実際に行われていた事は疑い様が有りません。『文政三辰年御渡』にも見られる様に、サイコロの代わりにカルタを使った長半賭博(多分前述の“試案①”のタイプ)は様々な時代の様々な場所で考案され、実際に行われていたで有ろうと考えるのが自然な理解でしょう。従って『教訓世諦鑑』の書かれた享保初期の大坂に“長半カルタ(仮称)”が存在していたとしても、決しておかしくは無いと考えます。
ところで、『賭博史』にせよ『賭博と掏摸の研究』にせよ、今迄に何度も目を通してきた資料でが、これらの箇所に関しては全く記憶に残ってはいませんでした。今回“長半カルタ(仮称)”を意識して読み直して見たところ、不思議なもので関係する箇所でピタリと目が止まるものですね。『文政三辰年御渡』にしても、たまたま別件で御仕置例を流し読みしていた時に目に飛び込んで来たもので、もしも“長半カルタ(仮称)”を意識していなければ気付かなかったと思われます。
江橋先生も『賭博史』『賭博と掏摸の研究』は勿論の事、『文政三辰年御渡』の文面も一度は目にされている筈と思いますが、“長半カルタ(仮称)”に関するこれらの記述に気付かれていたのかどうかが気になる所です。
逆に、当時の社会で真っ盛りであったに違いない「カブ」や「ヒイキ」の博奕に近いカルタ遊技についてはその遊技法についてまったく書かれていない。
これもおかしな批判ですね。当時の資料状況から見て、確かに「カブ(“かう”系技法)」はそこそこ盛んに行われていたと考えられます。しかし「ヒイキ(比伊幾)」はと云うと、唯一『雍州府志』だけに、しかも内容の説明も無く名称のみが記されているだけの、言わば得体の知れない技法に過ぎません。その事は江橋先生も良くご存じの筈です。にも拘らず、あたかも「ヒイキ」が「当時の社会で真っ盛りであった」かの様な書き方をされては困ります。少なくとも『雍州府志』以外には全く記録に残されていない「ヒイキ」が、『教訓世諦鑑』にも書かれていないという事を問題視するのは全くナンセンスです。
では何故“かう系技法”について触れられていないのかと問われれば、明快にお答えするのは難しいと言うしか有りません。無理にお答えするならば、前稿で触れた様に、単に“知らなかった”からだと考えるのが最も自然な理解でしょう。執中堂西山は、当時の賭博全体についてのかなり幅広い知識を持ってはいますが、サイコロ博奕や、カルタの“かう系技法”等の玄人賭博には疎かった様な印象を受けます。
貝原は、「三枚」というカルタ遊技の説明と、骰子の丁半賭博の説明とを混同して書いたように見える。これだけでも貝原が当時のカルタ遊技に通じていないままに執筆を急いだ事情が推測される。
「貝原が当時のカルタ遊技に通じていないままに執筆を急いだ事情」について先生は、少し後の部分で詳しく論証されています。そこでは貝原益軒の行動記録を基に実証的な検証が為されており、それなりに説得力の有る論証なのですが、残念ながら著者と成立年代の誤認に基づく誤った「推測」であり、実際には「カルタ遊技に通じていないままに執筆を急いだ事情」など有りはしません。
ところで、「三枚」にせよ「かう」にせよ、カルタの遊技法と「骰子の丁半賭博の説明とを混同」するという事態が実際に起こり得るのでしょか。もし「混同」したのだとしたら、どの様な状況で起こり得るのかを考えて見ましょう。
で、結局何が言いたいのかと云うと、江橋先生は「「三枚」というカルタ遊技の説明と、骰子の丁半賭博の説明とを混同して書いたように見える。」と軽くおっしゃりますが、それは先生の目にはそう「見える」と云う事に過ぎません。その様な「混同」が実際に生じる可動性は(絶対に無いとは言いませんが)かなり低いのではないか? と云う事です。
ところで江橋先生は唐突に「三枚」技法の名を持ち出されますが、執中堂西山は「三枚」というカルタ遊技の説明だとは一言も言っていません。「哥留多三枚をもつて」とは書いて有りますが、先生ご自身もここ迄は「三枚の札の」という読み取り方をされていました。これが「三枚」技法の説明だとする何等かの根拠がお有りなのでしょうか? 当方はこの部分をあくまでも“長半カルタ(仮称)”の説明として理解しておりますので、「三枚」技法と何等かの関係が有る様には読み取れません。
丁度いい機会なので、「三枚」について当方の思う所を述べさせて頂きます。
「三枚」は江戸の前期から後期迄、長きに渉って記録されているカルタ技法です。自信を持って技法の内容を説明出来るに至ってはおりませんが、少なくとも“かう”と同じく札の点数の合計が9を最高とする技法であり、遊技の手続きも“かう”と良く似ているのは間違い有りません。又、時代的にもほぼ“かう”とかぶっています。問題は“かう”と同じ技法の単なる別称なのか? その場合は地域によるものか? 或いは勝利条件や手続きの大筋は同じながら、何等かのルール上の明確な差異が有るのか? 判らない事だらけです。
更に、そもそも名称の「三枚」とは、何が三枚なのか? それは手札の枚数で間違い無いと思いますが、では前に揚げた『けいせい暁の鐘』に見られる「三枚のかう」の様に“必ず三枚”の札が配られる技法なのか? 或いは多くの“かう”系技法と同じく最初に二枚の札が配られ、三枚目の札を取るか取らないかは任意である、つまり“最大で三枚”なのか?・・・いくら考えても堂々巡りで、なかなか答えにたどり着けそうに有りません。こういう時は、取り敢えず保留としておくのが一番です。
ところで江橋先生は以前、ご著書『かるた』の中で「三枚」について次の様に述べられていました。
「三枚」は参加者に三枚のカードが配られて、その数の合計が奇数であれば勝ち、偶数であれば負けというシンプルな遊技である。同じく三枚ずつ配って、目数が高い方が勝ちで低い方が負けという遊技法も「三枚」と呼ばれていた。江橋崇『かるた(ものと人間の文化史 173)』
法政大学出版局 2015年 p.210
これには驚きました。さすがは江橋先生、「三枚」の謎を解明されていたのかと思いワクワクして読み進めたのですが、残念ながらこれで終わりで、又しても資料根拠が示されていません。仕方が無いので自分なりに推測しました。
この記述によれば「三枚」と呼ばれる技法には二種類のルールが有るとされます。
①に関してはすぐに『教訓世諦鑑』の記述に基づくものであると気付きました(ですよね?)。しかし余りにも雑な解釈である事は敢て当方が指摘する迄も無く、今回先生ご自身がさっさと撤回されている事からも明白です。但し、これが「三枚」についての記述だと云う認識は踏襲されて、今回の「「三枚」というカルタ遊技の説明と、骰子の丁半賭博の説明とを混同」したと云う判断に繋がっていると思われます。
②についてはかなり悩みました。「三枚」に関する資料を一通り見直したのですが、その様な記述は見当たりません。ならば江橋先生ご自身が発見した新資料によるものなのか? いや、それならば出典を隠すべき理由など有りません。うーむ・・・はっ!!
気付いてみれば簡単な事でした。これは“三枚ずつ配って、目数(の合計の一の位)が高い方が勝ちで低い方が負け”だと言いたいのだろうと思い至りました。つまり“かう”と同じ勝利条件の技法だという事でしょう(ですよね?)。
ところで江橋先生もこの当時は、「三枚」は各プレーヤーに札を三枚宛配るルールだとお考えだった様に見えますが、今は“三枚”を含む“かう”系技法は「二枚の札を配分された段階で、三枚目を要求するかしないかの選択権を持っている」「例外なく三枚で勝負する遊技法ではない」とお考えの様です。如何なる理由で考えを改められたのでしょうか? 悩み多き当方としてはとても気になるところです。
話があちこちに跳び過ぎてしまいましたが、結局この部分の最大の論争点は、江橋先生が主張する様に執中堂西山がサイコロの長半博奕とカルタ技法を混同した事による誤った記述であるのか、或いは実際に存在した“長半カルタ(仮称)”を実見した記録であるのか、どちらの可能性が高いかという問題になります。
江橋先生は「本当にあったのかも疑わしい」「混同して書いたように見える」という印象を持たれ、“長半かるた(仮称)”は執中堂西山の事実誤認によるものであり、実際は存在しないものとして葬り去りたい様です。更にはその様な事実誤認をしでかす著者による『教訓世諦鑑』自体が信頼性の無い資料だと印象付けたいのでしょう。
対して当方は、幾つかの(ショボイ)状況証拠を基に“長半かるた(仮称)”は実在した技法の記録であると考えています。しかし何れの立場にせよ、現状では決定的と言える証拠は有りません。どちらの主張がより現実的に見えるかは、読者の皆様の判断に委ねるしかありません。
(3)“よみ”について
続いては、お馴染みの“よみ”に関してです。
扨又九まひ六まひの数を以て一二三四乃至(ないし)九十、むま、きりと、よんで勝負をなすを、これをバ、よみと云ふ。
次に「よみ」の説明を見てみよう。一、二、三と数字を読んで勝負をするとあるが、『雍州府志』には記載されているような、親が手札を配分するという動作も、参加者が手札を「払いつくす」という動作も抜けている。貝原が書いているのは、札の「紋標数」を読むという動作だけなので、これでは数字の読み上げ合戦であってカルタの遊技ではない。「よみ」は「読んで勝負をなす」ものではなく、手札を早く「払い尽す」ことで勝負をする遊技である。札の「紋標数」を「読む」のは、「払い尽す」際のトラブル防止と勢いづけの掛け声であるに過ぎない。貝原の説明は方角違いである。読みは読んで勝負する遊技法とするのは、説明として不適切な表現である。
江橋先生は『雍州府志』の該当部分「人々得る所の札一、二、三の次第を数え、早く持つ所の札を払い尽くす、これを勝ちと為す。これを読という。和俗毎事、これを算るを読むという。」と比較して『教訓世諦鑑』の記述が不充分なものだと非難します。確かに『雍州府志』や『博奕仕方』と比べれば多少雑な説明である感は否めませんが、記されている内容は『雍州府志』や『博奕仕方』や、その他の“よみ”に関する諸資料の記述と何等矛盾するものではなく、“よみ”の基本原理を正確に捉え、簡潔に説明していると考えます。
先生のおっしゃる通り“よみ”技法の最終的な目的は最も早く手札を「払い尽す」事です。しかしそれは“よみ”を“よみ”技法足らしめている基本原理ではなく、所謂“ストップ系”と分類されるゲーム類の一般的な勝利条件に過ぎません。例えば“ババ抜き”も“七並べ”も“大貧民”も、何れも最も早く手札を「払い尽す」事を最終目的としますが、それぞれの技法の性格は全く異なっています。それは個々の技法の“基本原理”が異なっているからです。
“よみ”の基本原理は、札を読む(=数える)事によって手札を出して減らして行く(詳しくは「よみ」分室をご参照下さい)というものであり、それこそが“よみ”と云う技法名の所以でもあります。「よんで勝負をなす」という説明が「不適切な表現」とは到底思えませんし、寧ろ技法の本質を捉えた的確な説明であると考えます。「方角違い」なのは執中堂西山の説明ではなく、江橋先生の読み取り方のほうです。
それにしても、言うに事欠いて「これでは数字の読み上げ合戦であってカルタの遊技ではない。」という発言には唖然とさせられます。これは「カルタの遊技」に関する文脈の中で、当時最も盛んだったカルタ技法の“よみ”について記述した文章です。当時の読者は当方や江橋先生よりも余程“よみ”の事を良く知っていますので、この文章を読めば彼等の良く知るところの“よみ”技法の概略であると間違い無く理解したであろうし、執中堂西山も当然そう受け取られる積りで書いています。江橋先生は“同時代の読者がどの様に受け取ったか”という視点には全く無頓着ですが、『教訓世諦鑑』を読んだ当時の読者が、間違っても「数字の読み上げ合戦」だという間の抜けた読み取り方をしよう筈はありません。
又、当時のカルタ技法に関する予備知識を持ち、まともな読解力と批判力を有する現代の研究者が公平に判断するならば、誰が読もうともこれは“よみ”技法の説明以外の何物でも有りません。そもそもカルタ研究者である先生ご自身が“素直”に読めば、「数字の読み上げ合戦であってカルタの遊技ではない。」などと読み取れる筈は無いのですが、『教訓世諦鑑』を貶めたいが為に、単なる詭弁に陥っている事にお気付きでは無い様です。以前、江橋先生から「肝心なのは、史料に素直な気持ちで接することである。」というご助言を頂きましが、今はそのままお返し致します。
では何故、江橋先生が信条とされている“素直な読み”とは懸け離れた、傍から見ても明らかに“ひねくれた読み”をしてでも難癖を付けねばならないのかを考えましょう。
もしも『教訓世諦鑑』に記された「よみ」が、たとえ稚拙な記述であるにせよ『雍州府志』の「讀」と基本的に同じ技法の説明であると認めてしまうと、当然『教訓世諦鑑』の「あハせ哥留た」も『雍州府志』の「合」と同じものと考えねば辻褄が合いません。『教訓世諦鑑』の「あハせ哥留た」は常識的に考えれば“めくり系技法”の説明に見えます。又、当方は『雍州府志』の「合」が“めくり系技法”だと解釈し得る事も示しました。つまり両書の“よみ”と“合せ”は、共に連続性が有るという事です。両書の記述には整合性が有ると言っても良いでしょう。
対して江橋先生は『雍州府志』の「合」は“トリックテイキングゲーム”だとお考えですので、整合性を保つには『教訓世諦鑑』の「あハせ哥留た」も“トリックテイキングゲーム”である事を合理的に論証するする必要が有ります。勿論それが可能であるならばそうされたでしょうが、さすがに無理である事は理解されているのでのしょう。真っ向からの反論は断念し、次善の策として『教訓世諦鑑』自体が信頼性に乏しいものであり、そもそも使用に耐えない資料であると主張して、目障りな「あハせ哥留た」の記述を『教訓世諦鑑』諸共に葬り去ると云う作戦を採ります。その為には本丸である“合せ”の部分に対する批判のみならず、多少無理をしてでも“よみ”や“長半カルタ(仮称)”の記述や、全体の構成にも難癖を付け、外堀を埋める事によって『教訓世諦鑑』全体の印象を貶めたいのでしょうが、到底成功している様には見えません。
江橋先生が『教訓世諦鑑』という一つの文献に対して、百万言を費やして難癖を付けようとされる理由が見えて来ました。それは学問的に公平な立場からの史料批判には程遠く、単に自説である“合せ=トリックテイキングゲーム説”にとって都合が悪いからと云う不純な動機によるのは明白です。不純な動機による無理な結論に導こうとする余り、論理のあちこちで破綻を来していると言わざるを得ません。
二と二とを、合せ五と五とをあハせ、次第/\に、其かずに合せて、しやうぶをなすをバ、あハせ哥留たと云ふ。
続いていよいよ、最大の問題である“合せ”に関する部分に入ります。江橋先生にとっては最も目障りな部分だけに、相当気合が入っている様です。
江橋先生は“合せ=トリックテイキングゲーム”と云う立場を取られていますので、この部分の記述がトリックテイキングゲームの説明である事を論証するか、さもなくば記述内容が信頼出来ない事を立証して葬り去るしか有りません。先生の主張を見させて頂きましょう。
続いて「あはせ」の説明を見てみよう。「二」と「二」、「五」と「五」を合わせて、「次第しだいに」勝負をするとしか書かれていない。「二」と「二」をどう合せるのか。先入観を持たないでこの文章を読めば多義過ぎて文意不明である。他の参加者が打った「二」の札に自分も「二」の札を合せるというのであればトリック・テイキング・ゲームである。
この部分については前稿で「ある程度江戸カルタの遊技法についてご存じの方ならば、これが“めくり”や“てんしょ”の基本原理と良く似ているという事に異論を唱える方はいないでしょう。」と書きましたが、ここにいらっしゃいました。それにしても、これを読んで「トリック・テイキング・ゲームである」と読めるとは、どんだけ強い「先入観」をお持ちなのでしょうか。
先生のおっしゃる通り、この文章が曖昧で「多義」的である事には同意しますが、繰り返し言う様にそれは資料の信頼性とは何の関係も有りません。
ところで「文意不明」って何でしょうか? 言葉尻を捉える様で恐縮ですが、そもそも「多義」とは複数の意味に取れると云う事ですので、それが「文意不明」では論理的に矛盾しています。記述が多義的ならば解釈の選択肢が増えるだけの話ですので、それ自体が悪い事ではありません。複数の解釈を他資料や情況証拠と照らし合せて、どれが最も合理的な解釈なのかを考えれば良いだけの話です。
更に失礼を承知で言わせて頂けば、先生が資料批判に於いて平然と「文意不明」と言ってのける神経が当方には到底理解出来ません。勿論当方にも文意が全く理解出来ない資料は山ほど有ります。しかし、全ての資料はその著者の認識、意図に基づいて、読者に何かを伝える目的で書かれたものであり、少なくとも同時代の読者に理解される積りで書かれたものです。現代の我々がその意味を読み取れないのは、読む側の勉強不足の為に外なりません。
実際当方にも全く文意が理解出来ず、お手上げ状態だった資料が新資料の発見や、ちょっとしたヒントとの出会いや、突然のヒラメキによってスッキリと理解出来た経験が度々有ります。資料を「文意不明」と云う理由で切り捨てるのは単に読み取る側の怠慢であり、自らの不勉強を晒すだけの恥ずべき行為だと考えます。「文意不明」を根拠として資料の信頼性が低いと見なす論理を認める事は到底出来ません。
何故「他の参加者が打った「二」の札に自分も「二」の札を合せるというのであればトリック・テイキング・ゲームである」のでしょうか。明らかにトリックテイキングゲームの基本原理にそぐわない記述です。まあ、確かにゲームの最中にその様な局面が生じる事は有るでしょう。例えばオープナーが或るスーツの2をリードした時、同じスーツを持っていないプレイヤーが捨て札として他スーツの2を出したり、或いは切り札の2を出す様なケースですが、何れにせよかなり特殊な局面です。
もしも仮に“合せ”が“トリックテイキングゲーム”であるとすれば、まともな著述力を有する者ならばこの様な説明になる事は100%有り得ません(江橋先生に言わせれば、執中堂西山はまともな著述力を有していないと云う事になるのでしょうが)。又、普通の読解力を持つ読者(当時にせよ、現代にせよ)が素直に読めば、少なくともこれを札の強弱を競い合わせる“トリックテイキングゲーム”の説明であると理解する事は有り得ません(よね?)。
では何故江橋先生の目には、これが「トリック・テイキング・ゲームである」と映るのでしょうか? それは「合せる」と書かれているからに外なりません。
江橋先生の唱える“合せ=トリックテイキングゲーム説”は、「合せる」には“競い合わせる”という語彙が有り、カルタの“合せ”技法はこの意味である。つまり札の強弱を競い合わせる技法、即ちトリックテイキングゲームに外ならないと云う論理を根本としています。
「合せる」の古い語彙に、“競い合せる”という意味が有るのは事実です。例えば『日本国語大辞典』の「あわせる」の項には九種の語彙が示されていますが、最後の九番目(重要度や使用頻度が低い事を意味します)に「物と物、あるいは人と人とを比べる。比較する。また、物の優劣を比べる遊びをする。」と有ります。用例が4点揚げられていますが、内3点は平安時代成立の『宇津保物語』『枕草子』『源氏物語』で、最も新しいのが室町末成立の御伽草子『鉢かづき』です。普通は示されるべき江戸時代や近代の用例は示されていません。勿論丁寧に探せば近世以降の用例も見つかるでしょうが、少なくとも既に特殊な用法であったと考えて良いでしょう。
『教訓世諦鑑』が書かれた当時(十八世紀初頭)の著者や読者にとって“合せる”の主たる意味は、現代と同じく同種のもの、一対のものを“組み合せる”という意味であり、“競い合せる”という意味は特殊な文脈のみで通用するものです。当方は江戸文学に関して全くの素人ではありますが、それでも同時代のかなりの数の文芸作品に目を通して来た経験から自信を持って断言出来ます。(『雍州府志』については、文中全ての「合」を抜き出して検討し、“競い合せる”とは読み得ない事を実証済みです。)
当時の読者としては「二と二とを、合せ五と五とをあハせ」という文章を読んで“2と2を競い合わせ、5と5を競い合わせる”と解釈し、トリックテイキングゲームを思い浮かべる事は絶対に有り得ません。同じ数の札を組み合わせる技法としか読み得ません。
でも、そもそも手札を配分するという記述もないので、「合せる」元になる札がどこにあるのかも分からない。手札という記述がないのだから、場札を場札に合せる遊技法であろうか。表面を上にして晒されている場札と、裏面を上にして積まれている山札を合せるということになる。この動作は当時も今も「捲る」と表現されるのであるからまさに「プロトめくり」らしくなるが、ゲームとして単調過ぎて、到底、金銀を賭ける勝負には適さない。
先生はしつこく技法の詳細が分からないと批判されますので、こちらもくどく言わせて頂きます。執中堂西山はカルタ遊技の指南書を書く積もりは有りません。そこに書かれているのはカルタの遊技法では無く、技法の基本原理の説明であり、それを十分に果しています。確かに『雍州府志』に比べて情報量が少ないのは残念では有りますが、それは内容の信頼性とは全く関係有りません。
ところで、さりげなく「ゲームとして単調過ぎて、到底、金銀を賭ける勝負には適さない」と奇妙な事をおっしゃります。ならば、二つのサイコロの目の合計が偶数か奇数かを当てるというルールのゲームなど「単調過ぎて、到底、金銀を賭ける勝負には適さない」訳ですね。・・・これは単なる揚げ足取りですが、それぐらい先生の主張は混乱しています。
さらに、「二」の札と「二」の札を合わせたとして、その先がどうなるのかも書いてないから分からない。合せ捨てるのか、合せ取るのかが書いてない。合せ捨てることで手札が減り、早く打ち尽くしたものが勝ちとなるというのであれば、これは読みカルタの多少変形した遊技法である。合わせた札を自分の手元に釣り取るというのならフィッシング・ゲームになるが、釣り取るという動作の説明がないのでこの文章からこの遊技法であろうと考えることは難しい。
何をか言わんや。今度は「これは読みカルタの多少変形した遊技法である。」ですか!? 当時の読者は“よみ”も“合せ”も良く知っているのですから、その様なトンチンカンな読み取り方をしよう筈は有りません。そもそも“合せ”が「読みカルタの多少変形した遊技法」では無い事は先生ご自身重々ご承知なのに、ただただ難癖を付けるだけの為に、初学者を混乱させるだけでしかない無意味な記述は控えて頂きたいものです。
繰り返しになりますが、執中堂西山はカルタ遊技の指南書を書いている訳では有りませんので、競技の手続きの詳細まで事細かに説明する必要など有りません。確かに先生のおっしゃる通り記述が簡潔過ぎて、この文章のみからは“合せ”技法の実体は分かりません。しかし、カルタ技法について一通りの知識を持ち、普通の読解力を有する読者ならば、この文章が他の如何なる技法よりも“めくり系技法”の基本原理と似ていると感じると思うのですが、違いますかね? 少なくとも「トリック・テイキング・ゲームである」とか「読みカルタの多少変形した遊技法」だと感じる筈は有りません。
それに、「次第しだいにその数に合わせて勝負をなす」という言葉も気になる。「次第しだいに」とは何の次第なのか分からない。合せる札の順番に「一」「二」「三」という「次第しだい」があるのか。札を打ち出す遊技者の順番なのか。「次第しだいに合せて勝負する」と書かれると、どうしても参加者が順番に札を出し合うトリック・テイキング・ゲームが思い浮かぶ。
「次第しだいに合せて勝負する」なんて書かれていませんから! 「その数に」を抜いたら全く文意が変わってしまいます。自分に都合のいい様に自由に原文を切り張りして創作した文章を基に、「トリック・テイキング・ゲームが思い浮かぶ」と言われても困ります。先生は原文通りの「次第/\に、其かずに合せて、しやうぶをなす」でも「トリック・テイキング・ゲームが思い浮かぶ」とおっしゃるのでしょうか? まあ、多分そうおっしゃるのでしょうね。あくまでそう主張させるのでしたら仕方ありませんが、それは“合せる”の語意は“札の強弱を競い合せる”であり、即ちトリックテイキングゲームだという固定観念によるもの以外の何物でもありません。
繰り返します。これを読んだ当時の読者にしても、常識的な読解力を有する現代の読者にしても、先入観を持たずに素直に読めば、少なくともトリックテイキングゲームを思い浮かべる事は万が一にも有り得ません(よね?)。
そうではなくてフィッシング・ゲームなのだとすれば、参加者は順番に手札を出して場札と合わせて釣り取るけれども、それは「取り番」でそうしているのであって、合せるその動作で「勝負をなす」のではない。この場合は、「次第しだいに」数を合せるのではなく、「順に」ないし「番に」、つまり順番に数を合わせて、最後まで進んだら獲得した札の点数を数えて、その合計の多寡で「勝負をなす」のである。
ここ迄くると冷静な資料批判というよりも、ただ単に『教訓世諦鑑』の“合せ”の記述に関してはその一字一句に至る迄、全てに難癖を付けなければ気が済ま無いだけの様に見えてしまいます。
江橋先生は「次第しだい」の語意を、かなり限定的な意味に捉えられている様です。「次第しだい」を『日本国語大辞典』で調べると
しだい‐しだい【次第次第】②《副》(多く「に」を伴って用いる)物事が順を追って行くさま、状態が少しずつ変化するさまを表わす語。だんだん。つぎつぎ。
と有ります。つまり平たく言うと“順に”ないしは“順番に”であり、これが現代でも当時でも一般的な用法だと思われます。そうすると「次第しだい」は“めくり系技法”の説明としても何等不自然な表現では有りません。当方の解釈としては「次第/\に、其かずに合せて、しやうぶをなす」は“順番に、同じ数の札を組み合せて勝負をする”という意味に取るのが自然だと考えます。
なお、念のために書いておくが、江戸時代中期(1704~89)以降の上方の文献史料に登場する「合せ」、別名「てんしょ」という遊技がフィッシング・ゲームを指すことは研究者世界での共通の理解であり、私にも異論はないし、ほかに異議を申し立てた学説は知らない。だが、そうだとしても、江戸時代中期(1704~89)の文献史料である『教訓世諦鑑』の「あはせ」が他の文献史料に出てくる「合せ」と同じものを意味するのかどうかはよく分からない。
明和期以降に、主に上方で流行した技法である“てんしょ”(文献では明和五年(1768)の『傾城阿波の鳴門』初出)が、ほぼ同時期に江戸で流行し始めた“めくり”と同系統の技法だった事に異論は有りません。しかし如何なる根拠によって“てんしょ”が“合せ”の別名だとおっしゃるのでしょうか? ちなみに『カルタ』(p.188)では逆に「「テンショウ」(別名「合セ」)」と記されていますが、そこでもその理由には全く言及されていません。当方は「研究者世界」などには属さないアマチュアに過ぎませんので、その辺の事情についてはサッパリ分かりません。例え「研究者世界」では「共通の理解」であるにせよ、当方を含めた一般のアマチュア好事家にも理解出来る様に、丁寧な説明をお願いしたいところです。
ちなみに当方は、“てんしょ”と“めくり”とは共に、“合せ”の発展的バリエーションの関係にあると考えています。
当方が“合せ”は一貫してめくり系ゲームであると考えているのに対し、江橋先生の主張は、江戸前期迄の“合せ”はトリックテイキングゲームであり、中期以降の“合せ(=てんしょ)”はめくり系ゲームであると云うものです。この考えについては以前 “「あわせ」技法内容変化説(仮称)”と呼んで、その妥当性を考察しましたのでご参照下さい。江橋先生には、いつ頃、何故、その様な変化が起きたのかを丁寧に説明して頂きたいと願います。
続きを見させて頂きましょう。
たとえば、平成二十八年(2016)のNHK大河ドラマ「真田丸」に、豊臣秀吉と淀と真田信繁(幸村)が「三池カルタ」二組を使って今日のトランプの遊技法、「神経衰弱」をして遊ぶカットがあって驚いたことがある。「二と二とを、合せ、五と五とをあはせ、次第(しだい)ゝゝ((しだい))に、其かずに合せて、しやうぶをなす」遊技法だと言えば、この秀吉愛顧の「神経衰弱」はぴったり当てはまる。その他、さまざまな遊技法が想定可能である。そうした多様な例の中の一例としてこれをフィッシング・ゲームとしての「合せ」だと引き寄せて理解する説も不可能ではないし、それを全面的に除外する積極的な根拠もない。どうぞご自由にご想像ください、でもそれは、この記述はフィッシング・ゲームであってほしいという色眼鏡越しに見ているからそう見えているのであって、神経衰弱ファンが読めば、これこそ神経衰弱の世界最古の文献史料で、江戸時代中期(1704~89)にすでに日本にこの遊技法が存在していたことが証明されたとなる。貝合せのファンなら、これは場札と場札を合せる貝合せ風の遊技法を書いたものだとなる。つまり、このあいまいな文章自体から特定の遊技法の記述だと客観的に判断することはできませんね、ということである。
あー、「真田丸」には驚きましたね。あれが史実だと勘違いするオッチョコチョイな視聴者がいない事を祈ります。
勿論「さまざまな遊技法が想定可能である」というご主張には同意します。確かにこの文のみを見れば「神経衰弱」だとか「貝合せ風の遊技法」という解釈も可能でしょう。又「このあいまいな文章自体から特定の遊技法の記述だと客観的に判断することはできません」というご指摘にも全く異存は有りません。余りにも当たり前の事ですから。
「このあいまいな文章」単独での解釈では、それが如何なるものにせよ“主観的”な判断です。もし仮にこの文章が「あいまい」では無く、一義的に理解可能な明快なものだったとしても同じ事です。如何なる資料においても、それ単独での解釈では“客観的”なものとは言えません。“客観的”な判断とは、他の資料や状況証拠と照らし合せて合理的だと認められる判断と考えており、『教訓世諦鑑』についても、その様な方針に従って解釈しています。
例えば、当方の唱える“合せ=めくり系技法説”には、『教訓世諦鑑』の他にもう一点重要な基礎資料が有ります。
本書の刊行は寛政四年(1792)ですが、内容は寛保・延享期(1741-1748)の江戸の風俗を記したものですのです。『教訓世諦鑑』とは20年程しか離れていませんので、ほぼ同時代の記録と考えて良く、互いに補完しあうものと考えます。
大坂で記録された『教訓世諦鑑』の記述と、江戸で記録された『江府風俗志』の「合はかるたにて、数を合せ勝負する事也」と云う記述は、どう見ても同じ技法であり、さらに突込んで言えば“めくり系技法”としか考えられません。江戸と上方での一致と云う点では、共に貞享三年(1686)刊の『雍州府志』と『鹿の巻筆』との両方に“合せ”が記載されている事とも整合性が有ります。
想像するに、江戸初期から前期にかけての文化の中心地は上方であり、主なカルタ技法に関しても上方で流行したものが江戸に伝播したと考えられます。江戸前期の江戸と上方との間で、主なカルタ技法に差異が有ったらしき形跡は見当たりません。“合せ”技法も又しかり。江戸版である『鹿の巻筆』『江府風俗志』、京都版の『雍州府志』、大坂版の『教訓世諦鑑』に載る“合せ”は全て同一の技法だと考えるのが自然でしょう。
享保期頃から次第に江戸独自の文化が生まれて来たというのが一般的な理解ですが、“合せ”に関しては明和期に東西で大きな変化が起きた様です。“合せ”の発展的バリエーションとして、上方では“てんしょ”江戸では“めくり”がほぼ同時期に流行しています。ここに至ってカルタ技法に関しても、上方の影響から独立した江戸独自の発展が有ったものと考えています。
ちょっと話がそれてしまいました。元に戻しましょう。
当方は『江府風俗志』や、その他様々な傍証と合せて総合的、客観的に『教訓世諦鑑』を評価した結果として、これを“めくり系技法”だと解釈しています。
もしも『教訓世諦鑑』を読んで、江戸中期の“合せ”は「神経衰弱」だとか「貝合せ風の遊技法」だとか主張する御仁が現れたなら、当方としては“その可能性を支持する傍証を一点でも良いのでお示し下さい。”と言ってお引き取り願うしか有りません。もしも確かな根拠を示した上での主張ならば、当方としても検討するにやぶさかでは有りませんが、管見ではその様な資料は存在しませんし、今後発見されるとも到底思えません。
勿論、カルタに精通されている江橋先生ご自身が、真剣に「神経衰弱」だとか「貝合せ風の遊技法」だとお考えになる筈は有りませんので、ただ当方の解釈が恣意的なものであるという事を言いたいが為に、譬えとして出されただけなのは承知しています。しかし、まがりなりにも複数の資料根拠と論証に基づく当方の理解(勿論江橋先生もご承知の筈です)に対して、何等の根拠も無い「神経衰弱」だとか「貝合せ風」といったトンチンカンな例を引き合いに出されて「色眼鏡越し」などと揶揄されるのは甚だ心外です。
尚、「神経衰弱」も「貝合せ風の遊技法」も、同種のものを組み合わせてペアーを作り、それを取得するという形態の遊技であり、当方の考える“広義のめくり系技法”に属するものです。江橋先生もこの文章が“同種のものを組み合わせる”タイプの技法に読める事は認めていらっしゃる様ですね。
江橋先生はここ迄に、「トリック・テイキング・ゲームである」「読みカルタの多少変形した遊技法」「神経衰弱」「貝合せ風の遊技法」と様々な解釈が可能だと指摘する事で、その曖昧さ故に資料として信頼が置けないとされますが、それらの解釈の妥当性には全く無頓着です。当方は「トリック・テイキング・ゲームである」については、当時の一般的な“合せる”の語感から見て有り得ない。「読みカルタの多少変形した遊技法」については、他の資料との整合性から見て有り得ない。「神経衰弱」「貝合せ風の遊技法」については、資料的な裏付けが皆無である。この様な理由でこれらの解釈には妥当性が無いと考えて退けました。例えそう読み得るにせよ、そもそも全く妥当性の無い解釈を羅列する事で、その多義性故に資料自体の信頼性を否定しようとする論理には到底同意は出来ません。
また、細かな表記の問題であるが、この書で、「かう」「おいてう」「よみ」では「かうかるた」「おいてうかるた」「よみかるた」ではないのに、なぜ「あはせ」だけが「あはせかるた」と「かるた」が付いて表記されるのか分からない。
おっしゃる通り「細かな表記の問題」であり、余り重要とは思えませんが、先生が「分からない」とおっしゃるならば当方なりに精一杯お答えしましょう。
ところで、江橋先生はここ迄の批判の中で、何回「分からない」とおっしゃったでしょうか? 答えは9回です。このペースならば10回の大台突破は時間の問題でしょう。先生はご自分に「分からない」事が多ければ多い程、『教訓世諦鑑』の信頼性が弱まるとでも思っていらっしゃるのでしょうか?
先ず、再三述べている様に“かう”“おいてう”は技法名では無く、点数を表す符丁だと考えますので、“かうかるた”“おいてうかるた”などと書かれていないのは当然の事です。但し“かう”の場合は遊技法の名前でもありますが、管見では江戸期の資料で技法名として“かうかるた”と書かれた例は一例も有りません(“かぶかるた”は『好色梅花垣』の一例有り)。つまり技法名としての“かうかるた”という名称自体が存在しなかったか、もし有ったとしても極めて例外的な用法ですので、執中堂西山が“かうかるた”などと書く筈は有りません。
“よみ”に関しては“よみかるた(よみがるた)”という呼び方も多く見られます。但し“よみかるた”には二種類の用法が有り、一つは技法名として“よみ”と同じ意味で“よみかるた”と呼んでいるケースです。もう一つはカルタ札自体を指す場合で、特に歌かるたとの区別を明確にする為に48枚のカルタ(当方の言うところの“江戸カルタ”)の総称として“よみかるた”と呼んでいるケースです。御触書や御仕置例等の、賭博取り締まりに係わる公的文書に見られる“よみかるた”の多くはこの用法の様です。例えば、幕府の基本法典である『御定書百箇条』の「軽き賭之宝引よみかるた打候者」や、御仕置例で“よみかるたを打つ”とあるのは、必ずしも“よみ”技法に限定するものでは無く、“かう”“三枚”“きんご”や、恐らくは“合せ”も含めた、“よみかるた札”を使用する遊技全般を意味していると考えられます。この問題はカルタ史研究に於ける重要な観点ですので、後日稿を改めて詳しく論じたいと思います。
では、遊技法名としての“よみかるた”と、“よみ”とのどちらが多く使われているかと云うと、まあどっこいどっこいか、僅かに“よみ”が優勢かと云う印象で、どちらかが明確に優位だとは言えません。遊技法の名称としては“よみ”と“よみかるた”のどちらも有りです。
同様に“あわせ”に関しても、明らかに技法名としての“あわせかるた”も使われています。こちらも“あわせ”と“あわせかるた”との使用比率は半々位で、どちらかが明らかに優勢という事は無く、どちらも自然な表記だと言えます。尚、少数ながらカルタ札自体を指しているらしき用例も見られますが、それらは所謂“絵合せカルタ”と明確に区別出来ない用例です。
以上の様な認識に基づいて、江橋先生が「なぜ「あはせ」だけが「あはせかるた」と「かるた」が付いて表記されるのか分からない」とされた疑問の答えを整理しましょう。
先ず、ここでの「かう」「おいてう」は遊技法名では無く、数字の符丁と考えられますし、そもそも「かうかるた」「おいてうかるた」という言葉自体が存在しませんので、執中堂西山がそう書く訳は有りません。
では何故“よみかるた”では無く“よみ”とし、“あわせ”では無く“あわせかるた”としたのかを論理的に説明せよと言われると困りますが、敢えて言うならば、執中堂西山本人及びその周りの人達がそう呼んでいたのだろうと想像するしかありません。
ちょっとモヤモヤした答えに成ってしまいましたが、少なくとも執中堂西山の表記は当時のものとして不自然なものでは無く、寧ろ自然な表記だと受け取れると云う事です。江橋先生が疑問視する、表記の不統一といった現代的な感覚から難癖を付けられる筋合のものではありません。
続いても表記に関する疑問です。
「哥留(かる)た」という不慣れな、他の例のない異様な表記にした理由も分からない。賭博系のカルタの場合は「加留多」か「賀留多」であり、「哥留多」や「歌留多」は歌合せかるたの表示法である。「合せ哥留多」という表現には鰻重に箸ではなくナイフとフォークが付いてきたような、ゴルファーが野球のボールをピンに乗せて打とうとしているような、なんともちぐはぐな違和感がある。カルタ遊技について知っている者はこういう表現を絶対にとまでは言わないがまずはしない。
祝「分からない」10回突破!!!
当方は「哥留た」という表記に関して、特に違和感を覚えずに読み流していましたので、このご指摘には正直ドキッとさせられました。
ちなみに執中堂西山は、この部分では“カルタ”の表記として「哥留た」を使っていますが、他の部分を見ると「哥留多」「哥るた」更には「かるた」の表記も使用しています。彼は“カルタ”の表記法に特別なこだわりを持っている訳では無い様です。
先生のご主張は「賭博系のカルタの場合は「加留多」か「賀留多」であり、「哥留多」や「歌留多」は歌合せかるたの表示法である。」「カルタ遊技について知っている者はこういう表現を絶対にとまでは言わないがまずはしない。」従って、賭博系のカルタに「哥留(かる)た」という表記を使っている執中堂西山は、カルタの常識に疎い人物だという論法です。確かにこの主張には一理有ります。一理有ると言うのは、全く的外れな主張ではないと云う事ですが、残念ながら実際のカルタの世界はそんなに単純に割り切れるものでは有りません。
ここで、江戸時代全体で“カルタ”がどの様に表記されていたのか、手持ちの資料から概観しておきましょう。
江戸カルタ(一組48枚の賭博系カルタ)の表記法として圧倒的大多数なのは仮名表記の「かるた(カルタ)」で、500件以上確認しています。漢字表記自体が少数派ですが、その中では「骨牌」が約80件でダントツ一位、次いで「加留多」が20件、「賀留多」が13件といったあたりが主な所です。「賭博系のカルタの場合は「加留多」か「賀留多」」という先生の主張は不正確であり、これらは辛うじて多数派と呼べるかどうかと云うレベルでしょう。勿論、今後の新たなカルタ資料の発見によって数値は変化するでしょうが、全体の割合に大きな変動が有るとは考えられません。
その他の少数派で目に止まったものを、資料数の多い順に挙げますと「樗蒲」9件「軽板」6件「歌留多・哥留多」6件「加留太」5件「刈田」4件「紙牌」3件「嘉留多」2件「歌流多」2件。更に、単一の資料のみに見られるものでは「軽駄」「博牌」「博冊」「賭樗」「博子」「投牌」「奕牌」「角牌」等、実に様々です。
カルタに限った話では有りませんが、江戸時代の表記法の自由奔放さには呆れ返るばかりです。当時は国語審議会の様な機関などは有りませんので、各自好き勝手な表記をしても何処からも文句は言われません。これが便利だったのか不便だったのかは別にして、そういう時代だったのですから、現代人の視点からとやかく言ってもしょうがないでしょう。
勿論江橋先生も、これらの例外的な表記全てがケシカランと言っている訳では有りません。もしもその様な論法が成り立つのであれば、『雍州府志』で「賀留多」を用いた黒川道祐はセーフですが、「加留太」を使った『白河燕談』や『色道大鏡』の著者や、「嘉留多」を使った『人倫訓蒙図彙』の著者はケシカランと云う事に成ってしまいます。
江橋先生は少数派がダメだとおっしゃっているのでは無く、カルタの“カ”の音に“哥”を充てている点がお気に召さないのでしょう。その根拠は「「哥留多」や「歌留多」は歌合せかるたの表示法である」と云う点であり、これを江戸カルタに用いるのは「不慣れな、他の例のない異様な表記」とまで言い切られます。一方で「絶対にとまでは言わないが」と、珍しく予防線を張られておいたのは正解で、少数ではありますが明らかに江戸カルタの事を指している例が存在します。
これは判断に苦しみましたが、文中の“けなし”が“よみ”の役の一つですので江戸カルタの事と考えました
これも歌かるたの事である可能性は否定出来ませんが、庚申の日待ちの慰みで歌かるたと云うのは余り聞きません。似つかわしいのは江戸カルタでしょう。幾つか例を揚げておきます。
『俳諧今年竹』の「哥留多箱」は江戸カルタの箱と考えて良いでしょう。
「歌留多・哥留多」と同類の表記としてはもう一つ「歌流多」が有ります。
“哥”と“歌”は同字ですので、“カ”の音に“歌・哥”の字を用いた用例は『教訓世諦鑑』を加えた都合8点となります。
先生のご指摘の通り、江戸期の資料で「歌留多(哥留多)」とあれば、その殆どが“歌かるた”の事を指しているのは紛れも無い事実であり、これらの用例が例外的なものであるのは間違い有りません。しかし少なくとも「「哥留(かる)た」という不慣れな、他の例のない異様な表記」「カルタ遊技について知っている者はこういう表現を絶対にとまでは言わないがまずはしない」と云う認識は明らかに資料事実に反しており、江橋先生の誤解に外なりません。
又、「哥留多」という「異様な表記」をするのはカルタの事を良く知らない証拠だという論理を認めるならば、「哥留多」と近い「歌流多」という「不慣れな」表記を使った『大塔宮曦鎧』の作者もカルタについて良く知らない輩であり、彼の他の著作も含めカルタ記事としての信頼性は低いという事になってしまいます。『大塔宮曦鎧』の作者である近松門左衛門の著作がカルタ研究資料として使用に耐えないものであるとしたら、これは全てのカルタ研究者にとって大変ゆゆしき事態ですし、先生もご自身の著書『かるた』や、『日本かるた文化館』で近松作品を引用した箇所を削除せねば成りません。
江橋先生は「哥留多」という表記が「不慣れな、他の例のない異様な表記」だと感じられた様ですが、失礼ながらそれは先生の認識不足に基づく誤解であり、的外れな批判に過ぎません。
以上、江橋先生が“あわせかるた”の語に関して二つの観点から呈された批判について、何れも先生の誤解であると反論させて頂きました。
以上、要するに、この文章を素直に読めば、貝原の説明は簡単過ぎて、またあいまい過ぎて、遊技法の理解に必要な肝心な部分の説明が抜けていて、どういう遊技法を説明しているのか、文意不明で分からないのである。
執中堂西山にすれば、数百年後の研究者に分かるかどうかなど知ったこっちゃ有りません。しかし『教訓世諦鑑』は執中堂西山の個人的な日記や備忘録では無く、まがりなりにもは商業的な出版物ですので、当時の読者や版元にとっては「文意不明で分からない」ものである筈は有りません。
一見して理解困難な記述の意味を論理的に説き明かす事こそ、研究者の為すべき仕事だと考えます。自分の不勉強の為「文意不明で分からない」のならば、分かる迄は一旦評価を保留するのは恥ずべき事では有りません。寧ろ、同時代の読者が普通に理解したであろう文章を、自分には「文意不明」だという理由でその価値を否定して切り捨てるのは、真っ当な研究者の採るべき態度とは思えません。
試しにこの文章を江戸のカルタに関する先入観のない現代人に読ませて、文意をどう理解するかを尋ねてみるとよい。どのような遊技が紹介されているのか想像もつかないと思う。貝原の記述の信頼性は揺らいでいる。
はあ? 「江戸のカルタに関する先入観のない現代人に読ませて、文意をどう理解するかを尋ねてみるとよい」て? そりゃあ勿論「想像もつかない」でしょうよ。当方は今迄、その様な手法で歴史資料の信頼性を判定した例を見た事も聞いた事も有りませんし、勿論有効な方法だとは到底思えません。
まあ、もしも現代人を対象にするのならば、或る程度江戸期の文章読解に関する素養を持ち、且つ各種のカルタ技法について一通りのガイダンスを受けた人(つまり仮想当時の読者)「に読ませて、文意をどう理解するかを尋ねて」見たら面白そうですがね。間違い無く“めくり系技法”の説明だと感じられる方が大多数であろうと思われますし、少なくともこれを“トリックテイキングゲーム”だと感じる方は一人もいないであろう事は断言出来ます。
それにしても“合せ”の部分の最後に、まるで“これでトドメだ!”とでも言わんばかりに、この様な的外れな論理を持ち出されるのには全く理解に苦しみますし、それで「記述の信頼性は揺らいでいる」と結論付けられるのには唖然とさせられます。何としてでも目障りな『教訓世諦鑑』の信頼性を貶めたいお気持ちはお察ししますが、さすがにここ迄来ると、失礼ながら研究者としての真っ当な批判をする冷静さを失っている様にしか見えません。
さまざまの品ありと、云へとも、委しく記すに、及ばず。
自分の説明がツボを外していることは貝原も自覚していたのであろうか。「其しな又、さまざまありて、しろうとの、知りがたき、事なり」として自分は博奕の「しろうと」だからよく分からないのだと開き直っているが、ここに貝原の確信のなさが透けて見える。
ちょっと、ちょっと~。又これだ。いきなり何の説明も無しに、後のサイコロの部分の文章とすり替えないで頂きたい。
たしかに似た文章ではありますが、この部分は「委しく記すに、及ばず」であり、サイコロの部分が「しろうとの、知りがたき、事なり」です。この違いについては前稿で述べました。彼が“自分は素人なので詳しい事は知らない”と正直に告白したのはサイコロ賭博についてであり、カルタについてでは有りません。
これを全く同義の文章として論じたいならばそれも結構ですが、少なくともその旨を明示した上で、その理由を示す必要が有ります。もしも学生が卒業論文でこんなミスをしでかしたならば、指導教官から厳しく注意されるレベルの問題です。まさか読者をミスリードする為に意図的にすり替えているとは思いたく有りませんが、そうで無くとも余りにもお粗末な論証だと言わざるを得ません。
結局、この文章から分かるのは、宝永年間(1704~11)の、多分福岡に、「二」と「二」を合せ、「五」と「五」を合せるカルタの遊技があり、それを貝原が「あはせ哥留た」と呼んだという事実だけである。
この文には『教訓世諦鑑』が宝永八年(1711)に貝原益軒によって書かれたと云う、当方による誤った情報と、それに基づく論証結果が含まれていますので、その部分を修正して書き直させて頂けば
“結局、この文章から分かるのは、享保初期(1716-1721)の大坂(貝原益軒の居た福岡では無い)に、「二」と「二」を合せ、「五」と「五」を合せるカルタの遊技があり、それが「あはせ哥留た」と呼ばれていた事を執中堂西山が記録したという事実だけである。”
という事に成ります。
それ以上の意味、意義をここから読み取るのは、その読者の希望的観測であって、文献史料の客観的な解読法としては適切とは思えない。
このご意見には基本的に同意します。単一の資料はそこに書かれている情報が全てであり、それを自らの「希望的観測」による著者への「忖度」によって補足して解釈する様な手法は、「文献史料の客観的な解読法としては適切とは思え」ません。
くどく言わせて頂きますが、当方が心掛けている研究姿勢は個別の資料から得られた情報を、他の(出来れば複数の)資料から得られた情報との関係性によってその意味を読み取り、それらを総合的に解釈する事によって事実を説き明かそうと云うものです。それが「文献史料の客観的な解読法」だと考え、実践してきた積りです。
この後先生は、貝原益軒の著作だという誤った前提に基づいて、彼の経歴等から『教訓世諦鑑』の記述を益軒の地元である福岡地方での不十分な伝聞調査に基くものであろうと推測され、従ってその記述の信頼性は低いという論証を繰り広げられます。しかし『教訓世諦鑑』は貝原益軒とは無関係である事が判明しましたので、彼の著作である事を前提とした論証は無意味であり、取り下げて頂かねばなりません。当方の誤情報によって全く無意味な論証をさせてしまった事に関しては重ねてお詫び申し上げます。
しかし、この部分を削除すればそれで済むと云う問題では有りません。この部分は先生の論証全体に深く係わっています。
いずれにせよ、貝原は不知の世界のことを書いたのであり、記述の信頼性はあまり高くない。『教訓世諦鑑』は、全体としての評価はいざ知らず、少なくとも「博奕」の項は、カルタ遊技史の文献史料としては第一級のものとは言えない。このような文献史料を基礎に置いて歴史像を立論するのは危うい。大いに危うい。
江橋先生はここ迄『教訓世諦鑑』の記述内容を様々な角度から批判されていますが、終始一貫その中心として繰り広げられているのは、記述が「簡単過ぎ」「分かりにくい」「多義過ぎて文意不明である」といった論法です。先生はそうなっている根本の原因を「貝原は不知の世界のことを書いた」事に求めて、従って「記述の信頼性はあまり高くない」と結論付けられています。これはこれで論理的な主張では有りますが、残念ながら前提が崩れてしまっていますので、もはや全体の論理性が崩壊しています。記述が「簡単過ぎ」「分かりにくい」のは著者の知識不足による誤認、誤解では有りませんので、「記述の信頼性はあまり高くない」とする合理的な理由は存在しません。
当方の考えを繰り返しておきますが、執中堂西山には当時の読者に対して、カルタ技法の詳細を伝授すべき理由は有りません。技法の基本原理に関する必要最小限の説明に止どめただけの事であって、「簡単過ぎ」である事自体を非難されるべき筋合いは有りません。その記述内容の信憑性は、他の資料との整合性によって評価すべきものと考えます。
江橋先生はその外にも『教訓世諦鑑』の様々な記述に対して、様々な角度からイチャモ・・・いや、批判をされています。当方も意地になって悉くに反論を試みていますので、中にはこちらの方の分が悪いものも有るかも知れません。但し、先生の認識不足による誤解と思われる件については、具体的な資料根拠を示して反論しましたし、明らかに非論理的な論点については厳しく指摘させて頂きました。
江橋先生が『教訓世諦鑑』を「記述の信頼性はあまり高くない」「カルタ遊技史の文献史料としては第一級のものとは言えない」とお考えになり、ご自身のカルタ研究の資料として採用されないのは自由ですので、一々根拠を示せなどとやかましく言いはしません。しかし『教訓世諦鑑』を重要な依拠資料とする説(及びその論者)を批判する目的で、「記述の信頼性はあまり高くない」と主張するならば話は別です。最低限論拠の資料的裏付けが不可欠ですし、論理的に妥当な批判が求められます。
以上、当方の主張は全て書き切りました。結局、先生の主張される様に『教訓世諦鑑』の記述は信頼性に乏しく、カルタ研究の資料として使用に耐えないとして葬り去るべきものか、或いは江戸カルタ研究の基礎資料の一つとして認めるべきものか、その審判は読者の皆様お一人お一人に委ねるしか有りません。
尚、当方の立論が「危うい」ものである事は、先生に言われる迄も無く自覚しておりますが、それは『教訓世諦鑑』の信頼性が低い為ではありません。当方の主張する“合せ=めくり系技法説”は僅かな数の依拠資料と、幾つかの状況証拠によって導き出されたものですが、もしも当方の主張を根本的に否定する新資料を突き付けられたり(或いは、運良く自分で発見したり)、愚説の誤りを実証的、論理的に論破する批判を受けたならば喜んで自説を撤回、もしくは修正致します。しかし、資料的根拠にも論理性にも乏しい批判ぐらいではビクともしない程度の耐震性は持っている積りです。
研究室が、今後も『教訓世諦鑑』を信頼してそれに依拠するのであれば、その第三「博奕(はくゑき)」の全編について、カルタ博奕に続いた骰子博奕や、その後ろに書かれた雑な諸勝負の部分に至るまで素直に読み、書誌学的な検討も含めた全面的な再検討と鋭利な解析を加えて、その史料としての信頼性を納得させる研究成果を公表されることを望みたい。
当方は『教訓世諦鑑』がカルタ研究の基礎資料として依拠するに足るものと考えましたので、江橋先生のご忠告に従って再検討しました。その結果、書誌情報の誤謬という初歩的、且つ致命的な誤りに気付く事が出来ましたし、「鋭利な解析」かどうかは別にして「全面的な再検討」によって内容をより深く理解出来た積りです。これらは先生からのご助言が有ったればこその成果であり、心から感謝申し上げます。
で、今度は江橋先生の番です。先ずは『教訓世諦鑑』の原本を確認して頂いた上で、正しい書誌情報と全体の記述に基づいて再検討して頂かねば成りません。更に根拠とする資料の開示と、当方の批判に対する鋭利な再批判を頂ける事を心から願っております。